
階段の取っ手を荘厳に飾るナーガ
ラオスに行くきっかけを私にくれたのは、声を大にしては言えないが、某派遣先会社からの解雇だった。相当不当な突然の解雇に意気消沈しながら、5月の連休中は北アルプスを縦走していた。しかし、山岳会のメンバーに話を聞いてもらい、安曇野の町で荻原碌山、岩崎ちひろの美術作品に触れているうちに、不当解雇を「沸いて出た大型休暇」と前向きに捉える心の余裕が生まれてきた。
高校時代からの友人であるともちゃんが去年からラオスのビエンチャンに家族で駐在している。
「ラオスいいところだよ。私たちがいる間に一度おいでよ。」
彼女の言葉を思い出し、私は連絡を取った。そして地球の歩き方を見て、グーグルでラオスという国の輪郭を確認した。H.I.Sに感謝! 連休からはずれていたため、成田ービエンチャンの往復航空券が55000円で手に入った。
5月4日
成田空港からベトナム空港でホーチミンへ向けて出発。ホーチミンからプノンペン、プノンペンからビエンチャン。予定では午後8時にビエンチャン着であったが、プノンペンで機体不良のため4時間半遅延、しかし無事に飛行機は飛んで、夜中の12時過ぎにやっとパークビューというともちゃんの住むビエンチャンのマンションに到着した。
「あゆほちゃん、心配したよ〜。良かった。無事に着いて!」
「ごめんね。心配かけて。松崎さんもお久しぶりです! 遅くなってすみません。」
「大変でしたね。飛行機が遅延したんだってね。」
ともちゃんとご主人の松崎さんが出迎えてくれた。
2人は2003年にJICAの青年海外協力隊に参加し、フィリピンに滞在しているときに出会った。日本帰国後に松崎さんはJICA本社に勤務となり、3年前からラオスに駐在して仕事をしている。ともちゃんが赤ちゃんのりなちゃんを連れてビエンチャンに来たのは去年の秋で、私が彼女に会うのも約1年ぶりだった。
ともちゃんから頼まれて日本で買ってきた赤ちゃん用品を私はザックから取り出した。和光堂の粉ミルク缶2つ、グーグーの離乳食、ムーニーのお尻拭き。紙おむつはビエンチャンでも売られているが輸入品のため日本より高い。全て取り出すと私の荷物はすっかり軽くなった。
2人は12時を過ぎていたにも関わらず、ビヤー・ラオを空けてくれ、私の不運な近況を聞いてくれた。しかし今ここにいるのはその不運がもたらした結果である。人生、いいことばかりでも、悪いことばかりでもない。
2日前から、2人の友人であるフィリピン人のマリベルさんがラオスを旅行しにともちゃん家に来ている。しかし彼女は体調を崩して今ベッドで寝込んでおり、私が彼女に会うのは明朝となった。
5月5日
朝日が昇ると大きなガラス窓からは、日本の地方都市のような緑豊かで素朴なビエンチャンの街並みが見えた。マリベルさんの体調もよく、私たちはともちゃんに勧められて、朝ごはんの前にメコン川沿いの散歩に出かけた。
ビエンチャンはメコン川の左岸にある街で、対岸はタイとなる。パークビューから歩いて数分のところにその河岸はあり、赤土色の水流の上にある何もない国境線を見ながら、私とマリベルさんは歩いた。
彼女はフィリピンの大学で農学全般を教えており、ともちゃんが青年海外協力隊のボランティアをしている時に様々なアドバイスをした。それ以来の付き合いが続いており、今回ラオスを訪れることになった。2日前にタイ東北部のウドンターニ空港に到着してともちゃんと合流し、寺跡めぐりをしながらビエンチャンについたが、食べ物にあたり昨日は静養していたと言う。
「ラオスはどうですか?(How do you like Laos so far?)」
「まだそんなに見ていないわ。フィリピンの方がもっと洗練されている感じがするけど、悪くはないわね。
(Well, I haven't seen much yet. Phillipine is better and more sophisticated, but I think it is OK.)」
とややつれない返事。私のように感動屋さんではないらしい。
ともちゃんの家に戻ると 、テーブルの上には4品ものおかずが並んだ朝食が準備されていた。
「わあ、すごい。これ全部ともちゃんが作ったの?」
「いや。実はお手伝いさんなの。」
ともちゃんは苦笑して、りなちゃんをベビーいすに座らせながら答えた。今松崎家には、毎日午後ラオス人のコップさんがベビーシッターと家事をしに来ており、彼女がとても日本風のおかずを作るのが上手い。給料は1ヶ月約1万円。さらに、コップさんとは別にアルンさんという運転手にもヵ月1万5千円で働いてもらっている。ラオスの公務員の初任給が5〜6千円であることを考えると、1万円〜1万5千円はかなり高給となる。JICA駐在の人は地元にお金を落とすという意味もあって、ほとんどの場合お手伝いや運転手を雇うという。
朝食後、アルンさんに運転をお願いして、私は所用を済ませにビエンチャンの街に連れて行ってもらった。まず旅行代理店で明日のビエンチャンーバンビエン、明後日のバンビエンールアンパバーンの都市間バスチケットを取り、グリーンディスカバリーというツアー会社にて21〜23日のパック・オー地区の山岳民族の村を訪ねるツアーを予約して、再度パークビューに戻るのに何故か2時間半もかかった。
「ごめんね。ともちゃん、こんなに時間かかると思わなかったよ〜。」
「良かった。大丈夫、大丈夫。のんびりしているから。ラオスタイムは。」
今度はマリベルさん、ともちゃん、りなちゃんも一緒に、ビエンチャンの象徴であるタート・ルアンへと向かう。この金色に輝く仏塔は、13世紀のクメール様式の仏塔を修復したものと言われ、境内の庭も塔の基盤も正四角形なのが珍しい。参拝するための壇上に登る階段の手すりにはナーガと呼ばれる龍の彫刻があり、象の姿をしたガネーシャの像もある。一見するとヒンズー教のような感じを受けるが、れっきとした仏教寺院である。

タート・ルアンを出たところで、ちょうどオレンジ色の袈裟を着た僧侶のグループと出会った。タイからラオスに観光に来ており、英語の上手な1人は名門チュラロンコーン大学の卒業生であった。タイもラオスも、僧侶は身に纏うものとしてオレンジ色の袈裟しか持たない。しかし彼らのように休みを撮って旅行する僧侶も多く、袈裟と休日というコントラストが面白い。
りなちゃんを連れて一旦家に戻るというともちゃんと別れて、マリベルさんと私はJICA勤務の人たちがビエンチャンで一番と薦めるカオ・ソーイ麺のお店に入った。しばらくすると、もやしと肉味噌が乗った太麺が出てきた。あっさりしたスープに濃厚な肉味噌と湯でたてのもやしを絡めて食べるのがおいしい。また店頭で、長身痩躯、長髪を無造作に束ねたイケ面のお兄さんが、手際よく注文されたカオ・ソーイを茹で上げていたのも印象的であった。
午後は、ともちゃんの知り合いである保坂夫妻と一緒に児童保育園を見学しに行った。保坂さんの友人であるシューイェンさんはベトナム人でありながらラオスの教育に興味を持ち、児童保育園を設立、運営し始めて既に10年以上立つ。町の中心部から車で30分程走り、到着したその学び舎の前で保坂夫妻とシューイェンさんは抱き合って再会を喜び合った。
保育園の門の前には、紺色のスカートと白いブラウスのユニフォームを来て、手には手作りの花束を持ったかわいらしい子ども達が並んでいた。彼らはラオスの国家を歌った後、私たちに花束を渡し、シューイェンさんが学校の中へと案内してくれた。
門をくぐった校庭には、フランジャパーニ、マンゴー、ヤシの木などが育ち、木造平屋の3棟が並ぶ。シューイェンさんがこの学校では特に3R(リサイクル、リユース、リディース)運動を軸とした環境教育に力を入れていること、学校が終わった後はダンスや音楽、機織などの活動を自由に行うこと、資金調達としてキノコ栽培をしていることなどを説明しながら、校内を案内してくれた。
教室の中で机に座っている子供たちが窓からこちらの様子を窺っている。手を振ると笑って振りかえしてくれる子供もいる。
3時を過ぎて授業が終わり、エネルギーいっぱいの子供たちがわらわらと群れを成して校庭へ駆け出てきた。そして一目散に活動場所へと向かって行き、一瞬の休みも必要とせず、色んなことをやり始めた。
その中でひときわ目を引いたのが、小中学生の女の子達数人が始めた伝統舞踊の練習である。リーダーの女の子が前に立ち、その後ろに他の子たちが2列になって並ぶ。そして両手を胸の高さに持ち上げ、親指と人差し指で丸を作り、残り3本は手の甲にそらせる形を作った。私が遊び半分でその後ろに並ぶと、リーダーの女の子が私の前に来て、手の形を直してくれる。よかった、飛び入り参加が認められたらしい。まず手の動かし方と、足のステップの基本練習を行い、その後は音楽に合わせての練習が始まった。子供といえども、皆真剣で背筋を伸ばして凛とした眼差しを前に向ける。ゆっくりとした足のステップに合わせて、滑らかに手を動かす彼女らの踊りの中には、かわいらしさと妖艶さが同居しており、私は一緒に動きながら、彼女らの踊りに惚れてしまった。
踊りの写真ないのかな。
織物教室の子供たちは、子供の背丈に合った小型の機織り機でカラフルな布を織っており、音楽グループの子達はピアニカを使って国歌を歌う練習をしている。その横では新聞紙を使って袋やクラフトを作っている子供たちもいる。また、今日活動はしていなかったが、料理教室や劇を練習するグループもあるという。
一通りの見学が終わった後、スタッフの先生達も一緒に私達は職員室に集った。
「ここでは、スタッフの先生たちがそれぞれ得意なことを教え、子供たちも興味を持つことを学んでいます。皆さんは、何か得意なことがありますか?」
シューイェンさんにそう問われ、私は
「得意というほどではないんですが、空手を習っていて、、。」
というと、皆は目を見開いて
「やってみせてください!」
という。そこで、私は好奇心溢れる子供たちに、空手のつきや蹴りを教えてあげた(去年の秋に習い始めたばかりで、本当は教える技量などまるでないのですが)。
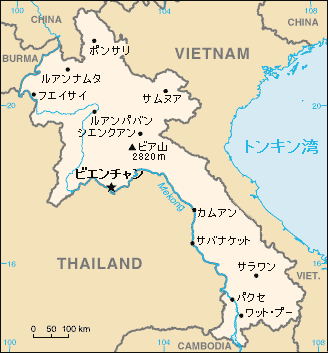
非常に思い出深い体験となった保育園を後にして、私達はアルンさんの運転でビエンチャンの街中まで帰ってきた。時刻はちょうど夕暮れで、私はパークビューの2キロほど手前で降ろしてもらい、メコン川沿いを散歩しながら帰ることにした。
5月は半年にわたる乾季がちょうど終わる時期でメコン川の水位が一番低く、堤防上の遊歩道からは白い砂浜のような河岸が広がっているのが見られた。そこでは地元の人たちが夕暮れのひと時を楽しんでおり、私もその”川浜”へ降りて砂の感触を踏みしめながら歩いてみた。川のたもとまで歩き、向こう岸のタイの集落を見つめ、その間を流れるメコンの流れが一見どちらが上流だろうかと迷うほど緩やかであることに驚く。チベット高原にその流れを発し、カンボジアで東シナ海に流れ込むメコン川は全長4023キロ。日本最長の信濃川は367キロ。日本列島とインドシナ半島では大陸の規模が違う。

私は河岸にある植物の写真を撮りながら歩いた。
夕日が沈み暗くなる直前にパークビューに帰ると、ともちゃんとマリベルさんが夕飯の準備をしていた。
「ごめんね。私じゃなくてお手伝いさんが作ってくれたものなんだけど、、。」
彼女がそういいながら並べたおかずは、ひじき、野菜の煮物、魚の炒め物、大根と干ししいたけを使ったお寿司と純日本風の物ばかり。盛り付けは彩がよくてかわいらしく、味のほうも日本で創作料理のお店が開けるのではと思うほど。ビエンチャンでラオス人のお手伝いさんが作ってくれた日本食に感動する夜となる。
パークビューの下の階に、ルアンナムター出身でツムラ勤務の日本人男性と結婚したジョイさんが住む。一男一女の母親でともちゃんの主婦友達でありかつラオス語の練習相手でもある。彼女の従兄弟がグリーンディスカバリーに勤務しており、私が参加するツアー料金を値引きしてくれるかもしれないと言うことで、夕飯の後に訪ねた。
ちょうど夕飯時だったにもかかわらず
「いらっしゃーい。入って入って。」
ジョイさんは言って麦茶を出してくれた。そして
「ツアーの値段のディスカウントですよね。ちょっと電話してみます。」
と携帯を取り出す。ジョイさんはしばらくその従兄弟と話していたが、私が今日既にクレジットカードで支払いを完了させているので難しいとのことだった。
「ごめんねー。力になれなくて。」
「いえいえ、そんなことないです。ありがとうございます」
私はそういいながら、机の上においてある、ジョイさんが美しい民族衣装を着た結婚写真に目を向けた。漢方薬のツムラに勤務しているご主人は、ラオスのルアンナムターで薬効を持つ植物の調査研究を行っており、その時に2人は出会った。数年後には、家族で東京に住む予定だと言う。
「東京に住むの楽しみです。でも緊張します。東京はどんな所ですか?」
「ビエンチャンよりは、ずっと大きいし忙しい街だけど、。色々なものがあるしおもしろいと思いますよ。」
とともちゃんと私は意見を述べた。ジョイさんの堪能な日本語なら、東京生活もすぐに慣れ、子供2人はあっというまにバイリンガルになるだろう。
5月6日
朝早く起きた私は、ともちゃんに一声かけて街中をランニングしに出かけた。昨日歩いたメコン川の堤防上の遊歩道をゆっくりと走りながら南下し、その後は街中の道を選んで北上した。途中寺院の近くで野良犬に追われ、噛まれて狂犬病にでもなったらどうしようと大慌てで逃れ、汗が止まらない状態でパークビューに戻ってきた。
家の中では、ともちゃんが台所に立つ傍ら、出社前の松崎さんとマリベルさんがりなちゃんと一緒に遊んでいた。テレビにはNHK-BSの日本のニュースが流れ、一瞬ラオスにいることを忘れそうになる。松崎さんは玄関先でりなちゃんに何回も手を振って、私たちより一足先に出かけていった。
今日の朝食は、今ビエンチャンで人気のスカンジナビアというベーカリーのパンと卵と野菜。
「昨日、今日と、まだあまりラオスの食べ物に接していないね。」
といいつつも、ラオスはフランスの元植民地だったことから、その文化的要素が色んなところに色濃く刻まれている。街中で売られているバゲットやクロワッサンは本場の味に近いところが多く、またフランスからの旅行者、仕事での駐在者も多く、街中の表示や観光名所の説明版などもフランス語のものが多く見られる。

私は今日一人でバンビエンへ出発し一泊して、翌日ラオスの世界遺産であるルアンパバーンの街へと向かう。ともちゃんとマリベルさんは、今日はビエンチャンの市内観光をして翌日飛行機でルアンパバーンへ向かう。その日の夜に私たちはルアンパバーンのラーサープラバーンホテルで同宿する予定である。
ゆっくりと朝食を楽しんだ後、私は二人に別れを告げて、パークビューの1階に下りた。しばらく待っていると予定通り9時30分にトゥクトゥク(かわいらしい絵柄の書かれた乗り合いバス。バイクに馬車がくっついたみたいな形)が迎えに来て、私はそれに乗り込んだ。トゥクトゥクはバス予約のある人たちの宿泊先に立ち寄りながら街中のバスターミナルへと進んでいく。
あるモーテルの前で、バックパッカーの白人男性2人が乗り込んできた。そのうち1人が私のことをじっと見つめて
「君、植物好きでしょう? (You like plants, don't you?)」
私は思わず息を呑んだ。間違っていない、私は植物が好きである。しかしなぜそれが初対面の人にわかるのだろうか?
「昨日の夕方、メコンの川岸で植物の写真撮っていましたよね。僕達もちょうどその頃散歩していました。」
そう言われて謎が解けた。彼らはアルゼンチンから来ており、東南アジアを中心に既に2ヶ月旅をしている。長期の旅行、うらやましい限り。若く見えるが実はやり手の実業家なのだろうか、などと思ってしまう。
バスターミナルで都市間バスに乗り換えると、隣に座ったのはニューヨーク生まれの男性だった。彼はツアーガイドとして働いており、今このバスに乗っている20名を連れて約2ヶ月に及ぶ東南アジア旅行の途中だという。ツアーはベトナムのハノイから始まり、ホーチミンまで南下、カンボジアに入りプノンペンとアンコールワットを見て、南からラオスに入国。ビエンチャンを出発しバンビエンに向かう行程ががまさに今日で、その後はルアンパバーンを見て、ルアンナムターまで北上。北部タイに越境して再度南下を始め、チェンマイ、バンコクを見てマレー半島を通過し最終目的地のシンガポールに到着する。
ツアーは地域ごとに区切られているので、例えばハノイ〜ホーチミン間のみに参加する人もいれば、全行程を旅する人もいる。長い旅の間には、ガイドとお客という関係性を超えた絆が生まれ、複数回訪れている町でも毎回新たな発見がある。しかしガイドの給料はたいした金額にはならない。
「僕は調理師の免許も持っているので、ニューヨークが観光客で賑わう夏の間はレストランで精一杯働くんだ。そのお金でなんとかガイドの仕事を続けているよ。」
世の中には様々な人がいて面白い。
午後2時、予定より約2時間ほど遅れてバスはバンビエンのバスターミナルに着いた。外は蜃気楼が立つかと思うほど熱く、私は国道を渡って街の中心部へと向かった。
バンビエンは、ビエンチャンとルアンパバーンの間に位置するメコン川沿いの集落で、石灰岩の奇岩が立ち並ぶ風光明媚なこの街には一泊する観光客も多い。私は今日の宿であるパンズプレイスというゲストハウスに荷を置き、洞窟が見学できるバンビエンリゾートに散歩しに行った。
メコン川にかけられた紅い橋を渡ると、高さ100メートル近くの巨岩が目の前に迫ってくる。その麓に洞窟への入り口があり、入場券を買って、私はひんやりとしたその中に足を踏み入れた。中は立派な鍾乳洞であったが、乏しい照明しかなくて足元は薄暗く、見物客はどうやら私一人しかいない。持っていたヘッドランプで足元と前方を照らし、恐る恐る奥へと続く道を歩いてみた。道は所々せまくなり、水滴が落ちるとその音が妙に洞内に響く。時々気配を感じてはっと後ろを振り返ってみる。しかし、そこには誰もいない。
一通り全ての道を歩き、鍾乳洞の入り口へ出てくるまでの約20分私はずっと一人だった。幽霊の存在を信じるわけではないが、外に出て日の光に当たった瞬間、何にも襲われなかったことにほっとして思わず深いため息をついた。
すぐ目の前には、小さな川が流れておりそこでは地元の人が、15人近く水遊びを楽しんでいた。頭上には熱帯の灼熱の太陽が輝いている。この天気なら濡れても洋服はすぐに乾くだろう、私はそう思い、ザックを置いてその川の中ににドボンと浸かった。両手と胃袋が引っ張りあげられるような浮遊感、そして冷却感。流れに身を任せながら両手で大きく水をかく。私は地元民と混ざって、つかの間の水遊びを楽しみ、水に浸かることの良さを改めて感じた。
夕方が近づき少しずつ日が傾いてきた。小川から上がった私は、その流れに沿って踏み跡のある道を歩き始めた。チークツリーの植林をぬけ、沢にかかった丸木橋を渡り土手を上がると、そこには広々とした水田地帯が広がっており、農耕用の牛が数頭歩いていた。遠方に見える幾つもの巨岩の姿はまるで中国の桂林のようで、謎の巨人が一人楽しみながらおもちゃの岩を並べたようにも見える。田植えは雨季の始まる6月であり、今は刈り取った稲の残りが乾いた大地に淡々と残っている。奇岩の景観に圧倒されながら、その田んぼのあぜ道を歩いて行くと、途中で農作業から帰ってくる村人達に出会った。どちらからともなく、なんとなく会釈をする。認識はしつつも積極的に声をかけたりしないという態度が日本人に似ている、と思う。
田畑の中を1時間ほど歩いて、メコン河岸に帰り着いた。対岸はもうバンビエンの中心部で、川の中では投網で魚を取っている親子がいる。私は街中の屋台でバナナパンケーキを買い、再度河原に戻ってその親子の様子を見つめた。投げては引き上げ、投げては引き上げ、という作業を繰り返しているが、ほとんど魚は取れていない。かかったとしても小魚である。ふと、多摩川にて投網で鮎を獲っている人のことが思い出された。
その後、街の中を歩きながら私は、観光客向けのレストラン、マッサージサロンやツアー会社の多さに改めて驚いた。あるツアー会社の前を通りかかると、
「Do you want to do kayaking? It's good fun. (カヤッキングはどうですか? 面白いですよ。)」
と声をかけられたので
「Sorry I am not interested in kayaking, but do you any good place to eat around here? (カヤッキングはあまり興味がないのですが、この辺においしいご飯どころはありませんか?)」
と逆に尋ねた。
「A place to eat. Well,, I don't know very well.(食べるところですか、、。あまり知らないです。)」
「Really? No favorite restaurant?(本当? お気に入りのレストランとかないですか?)」
「My favorite is my home! (僕のお気に入りは、うちですよ。)」
との回答。確かに地元の人にしてみれば、レストランの値段はとても高く、一番なのは家庭の味なのだろう。結局そこから少し歩いた所にある中華料理屋に入り、鶏肉の炒め定食を夕飯に食べた。
パンズプレイスに戻りシャワーを浴びると外は既に暗かった。私は宿の外にある椅子に腰掛けながら虫の声と涼を感じた。何も考えなくていい、頭の中身が緩む。ほっとして眼を閉じる。
5月7日
早朝に自然と目が覚め、町の中を散策しに出かけた。昨日は歩かなかった街の一角に寺院があった。境内には、ビエンチャンのタート・ルアンのように、ナーガ龍や金色の仏陀像があり、私以外誰もいない。本堂の中に一人しばらくたたずんでいると、手に籠を提げた地元のおばさんやおじさんが一人、二人と入ってきた。彼らは籠の中から銀のプレートとお皿を取り出し、その中にご飯やおかずをよそいはじめた。徐々に人の数は増え、皆一様に供物の準備をし、床に敷物をしいて、礼拝時に使うシルクの布を肩から斜めがけにした。
そっと本堂を出て境内の外を窺うと、托鉢を終えた十数人の僧侶がちょうどこのお寺に帰ってくるところだった。彼らはまるで空気か風のように、静かに、境内そして本堂の中に入ってきた。地元の人たちはよそった供物を壇の前に並べ、自分達はそれより下がったところに座り、僧侶達に手を合わせる。私も一番後ろのほうで同様に手を合わせて頭を垂れた。僧侶は壇上に一列に並び、真ん中の一人が仏陀像の正面で何かを唱えた後、全員で声を揃えて読経を始めた。
私は一瞬虚を突かれた感じがした。それはまるで「歌」だったのである。
旋律をともなった言葉の波が堂内に駆け巡ってゆく。
オーケストラの演奏や聖歌隊の合唱を聴くときに、背中に電流が走るような感動を覚えることがある。壇上は舞台、僧侶は演者、そして読経の中にはそれと同様の何かがあった。
半時間ほど経ち、最後にお鈴の音が響いて読経は終わった。と同時に心地よく張り詰めていた堂内の空気はやわらかく緩んだ。僧侶は私達のほうに向き直り、何か講話らしきことを話し始めた。意味はわからないが僧侶と地元の人たちとの間の、熱心に聞き、話すという関係性が感じられる。それが済むと一番若い少年僧が前に進み出て、食物が載せられた銀のプレートを持ち上げて運び、僧侶達は物静かにそれを食べ始めた。
地元の人たちは一礼して本堂を出てゆく。私も両手を合わせて、この場に居合わせたことに感謝し、そっと寺院を後にした。
ちょうど町の中は色々と活動を始めていた。私は店頭で大きな鍋を使って麺をゆでているお店に入り、朝ごはんにヌードルと米粉で作られた春巻きを注文した。ゆでた麺を勢いよく器に移し、にんにく、パクチー、ねぎをちらし、ざっとスープをかける。そして野菜を入れた春巻きを作り、ソースを添えてテーブルに出す。そのおばちゃんの手際の良さがすがすがしい。かつ味もおいしい。
街中の教科書や文房具を扱うお店で、子供用のラオス語の絵本を買った。クレヨンで書かれた挿絵から、クモ王子が主人公で旅をしながら色々なハプニングに合う話であることがわかる。しかし細かい内容はどうなっているのだろう。
パンズプレイスに戻り、フロントにいるスタッフに内容を訳してもらえないだろうかと尋ねた。驚いたのは、その中の20歳ぐらいの男の子が字が読めないことだった。ラオスの識字率はどのぐらいなのだろうと一瞬胸が痛くなった。別の女の子はラオス語も英語も堪能で、彼女は快く絵本を受け取り、1ページずつ読み始めた。
第1章 くも王子、色んな食べものに目移りする。
くも王子をご飯を探して草原を歩いていました。そこで出会ったのがキャッサバさんです。
キャッサバさんは言いました。
「僕は、茹でたりふかしたりして食べるのがいいよ。おいしいよ。食べてみるかい?」
くも王子は、食べたくなりましたが、もう少し空腹を我慢してもいいかなと思いました。
「ふーん、そういう食べ方も悪くないね。ちょっと考えてみるよ。」
くも王子は、そう言ってキャッサバさんのところを立ち去りました。
次に出会ったのは、バナナくんでした。
「僕は、生で食べると甘くておいしいよ。食べてみるかい?」
くも王子は少し考えて
「それもおいしそうだけど、ちょっと考えてみるよ。」
そう言って、バナナくんのところを立ち去りました。
その次に出会ったのは、お米さんでした。
「私は炊くとおいしいの。食べてみますか?」
炊くのには時間がかかりそうです。
「そういう食べ方も悪くないけど、もう少し考えてみるよ。」
そういってくも王子は、お米さんのところを立ち去りました。
大分暗くなってきました。くも王子はさらに歩き回りましたが、もう別の食べ物には出会いませんでした。そして結局、その日はくも王子は何も食べることができませんでした。
第2章 くも王子、亀くんとの夕飯
ある日、くも王子のところに亀くんが訪ねてきました。ちょうどその時、くも王子は鳥の丸焼きを夕飯に食べようとしていました。
「亀くん、よかったら夕飯を一緒に食べませんか?」
「わあ、うれしい。どうもありがとう!」
「でも、まず手を洗ってこなきゃダメだよ。この家の後ろをずっと行くと川があるからそこで手を洗ってくるといいよ。」
そう言われた亀くんは、その川に行って手を洗い戻ってきました。ところが、その間にくも王子はごちそうを全部自分で食べてしまったのです。
「亀くん、君は歩くのが遅いなあ。待ちくたびれて食べてしまったよ。」
意地悪く言うくも王子。亀くんはがっくりして帰っていきました。

ある日くも王子は、亀くんにいいました。
「この間は僕は君を夕飯に誘ったんだから、今度は君が僕を夕飯に誘ってもいいんじゃないかい?」
「わかった。じゃあ僕の家は沼の底にあるから、明日の夜に来るのはどうだい? 色んな魚のご馳走を用意して待っているよ。」
くも王子、楽しみにしながら亀くんの家に向かいます。
「あった、あった。あの沼の下だな。」
そこにもぐろうとしましたが、くも王子の体は軽く水に浮いてしまいます。
「亀くん、僕はもぐれない。どうしたらいいだろう。」
「なら、この上着を着ればいい。ポケットに石が入っているから、浮かばずにもぐることができるよ。」
亀くんにそう言われて、くも王子は渡された上着を着ました。ところが、今度は石によってくも王子の体はぐんぐん沈んでいき、くも王子は息をすることができません。上着を脱ごうと大慌て! 大変な目に遭いました。
くも王子、なかなかどうして憎めない。
第3章では、くも王子が仏陀に出会う挿絵があったので、どう展開するのかと非常に気になったが、ちょうど乗車予定のルアンパバーン行きのバスの時刻になってしまった。私は彼女にお礼を言って、その本をザックにしまった。続きは、日本に帰ってから誰かラオス語の話せる人に読んでもらおう。

パンズプレイスの前からトゥクトゥクに乗り、バスターミナルで都市間バスに乗り換える。今日の旅程は昨日の約1.5倍の7時間。11時過ぎに出発したバスはバンビエンの街を後にし、すぐに山岳地帯を進むようになった。
快晴の青空を背景に、石灰岩で形成された巨岩がいくつも立ち並ぶ。2時間ほど進んだとき、今までのものを凌駕する圧倒的な大きさを誇った岩体が窓の外に見えた。思わず瞬きをすることを忘れた。この地域ではこの岩山は聖山だろう、私は直感的にそう思った。道路はその山麓を巡るように走って行く。異なる角度から眺めることで、その巨岩は様々な表情を見せる。
途中食事と休憩を兼ねて下車した山間のお店では、一見東南アジアの人かと思うほど色濃く日焼けした日本人のお兄さんに出会った。
去年の秋に日本をたち、旅に身をおいて早7ヶ月。うち2ヶ月はインドでヨガを習っていた。ヨガはリラックスや肩こりにいいと言われるが、彼が習った本場のヨガは限界まで体の関節を曲げ、甚だしい筋肉痛に襲われる代物だった。私はルアンパバーンに到着した後、2泊3日の山岳トレッキングに行く予定であることを話し、もし興味があればと彼を誘った。
「いいなあ。山登るのとか興味あるんですけど、僕ラオスのビザがある数日で切れるので、その前に国境を越えて中国に抜けなきゃいけないんです。」
彼の旅はまだまだ続く予定らしい。
バスに乗り、さらに揺られること数時間。一日中大地を照らした太陽はいつの間にか山の端に隠れ、窓の外の景色は深い闇に包まれるようになった。そして午後7時、ようやくルアンパバーンのバスターミナルに到着。他の観光客とともにトゥクトゥクに乗りかえ、私はともちゃんとりなちゃん、そしてマリベルさんが既に到着しているラーサープラバーンホテルに向かった。メコン川沿いにそのホテルはあった。車体の上に載せたザックを降ろしてもらい、建物内に入ると、後姿に見覚えのある女性がフロントのカウンター越しに何かを尋ねている。
「あれ、ともちゃん?」
私の呼びかけに振り返ったのは予想通り彼女だった。明日行く予定の洞窟&象乗り体験ツアーの詳細を尋ねていたという。その話に決着がつき
「よーし! 明日はりなちゃん、初めての象乗りだ!」
と喜ぶ彼女に部屋に案内され、一息ついた後、4人は夕飯を食べに夜の街へと繰り出した。プラバーンホテルは博物館のすぐ隣にあり、その前の通りは夜には無数のお店が並ぶナイトマーケットになる。その賑やかな雑踏の中をくぐり抜け、私達は屋台通りに入った。ここは好きな屋台の前で、好きなおかずを注文し、それらをテーブルに運んで食べる。私達が選んだのは、ルアンパバーンソーセージ、春巻き、野菜炒め、かぼちゃの煮物、そしてカオ・ニャーオ(もち米)。ともちゃんと私は、日本を遠く離れたラオスの屋台の一角でともにビヤーラオを飲めることに乾杯する。
5月8日
まだともちゃんとりなちゃん、そしてマリベルさんが熟睡している時に私は目が覚めた。ランニングをしようとホテルの外に出て角を曲がると、ちょうど托鉢の時間だった。前のほうから何十人ものオレンジ色の袈裟を着た僧侶が托鉢壷を肩から提げて歩いてくる。路傍には、地元の人達がお櫃に入ったもち米や菓子などの供物を用意して座っており、通り過ぎる僧侶の壷の中に一掴みずつ入れてゆく。神聖で静寂で犯してはいけないその様子を少し離れたところから見守っていると、地元のおばちゃんが身振り手振りで
「供物を捧げますか?」
と尋ねてきた。どうしようかと
思いやや首をかしげて笑うと、彼女は私の手首を掴んで道端に座らせ、
「こういう風にやるんですよ。」
と籠を持たせた。私はあわてて、目の前を歩いていく僧侶達にお菓子を捧げた。頭は皆坊主なれど、その中には老いも若きも混ざっていて、何故か懐かしい気持ちになる。一籠分がなくなったので私は立とうとしたが、おばちゃんは
「ほら。また来るわよ。」
と肩を押さえ、それを続けているうちに、私は3〜4籠分もの供物を捧げることになってしまった。
困ったのはこの後で、なんと彼女はお金を請求してきたのである。私はランニングに行く途中だったので無一文であり、かつラオス語がわからなかったので、わざとらしく肩をすくめて、堂々とその場を離れて走り始めた。それにしても少しやり方が姑息である。
私はメコン川の支流を越えた街の反対側まで走った。塔のある小高い丘に登り、盆地状になっているルアンパバーンの街を見下ろした。途中道に迷ったりしたが、人に道を尋ねて、約1時間かけてラーサープラバーンホテルに戻った。
シャワーで汗を流した後は、4人でメコン川に面したオープンテラスでの朝ごはんとなった。バゲットとジャム、卵料理に濃いコーヒー。フランス植民地時代にラオスに根付いた食文化なのだと気付く。ともちゃんは、りなちゃんに離乳食を食べさせつつ、自分の朝食も食べたりと忙しい。
9時過ぎにツアー会社のバンが到着し、4人はルアンパバーンから北へ約40キロ、メコンの支流沿いにある象のりの村へと向かった。ガイド君は赤いTシャツがよく似合う元気な20代の男の子で、
「象乗りは初めてですか?」
「私は2回目で、あとの二人とこの子は今日が初めてです。」
とともちゃんが返事する。
到着した村の広場には立派な象が三頭いた。人慣れしているため、近寄っていっても象は比較的落ち着いており、むしろ動揺しているのは象を初めてまじかで見るりなちゃん。
ガイド君と象使いの男の子が、象の背中と同じ高さの昇り台から鞍を乗せて準備をしてくれ、私達はそこから象に乗ることになった。
「鞍じゃなくて、首に乗ってもいいよ!」
というガイド君の言葉を、私は聞き逃さなかった。通常首には象使いが乗るが、今日は歩きながら先導するので私が首に乗っても差し支えないという。恐る恐るまたがった象の首は、ごつごつしているが血の通った皮膚の感触があり、その後ろの鞍の座席にマリベルさんが座る。そして次の象にともちゃんとりなちゃんが乗り、2匹の象は象使いの少年の掛け声に従って広場から道路へ出て、快晴の下悠々と歩き始めた。
動物に乗る。これは子供ばかりでなく、純粋に大人も楽しい。りなちゃんも最初はお母さんの腕の中でニコニコしていたが、そのうち自分達が巨大な動物の背に揺られているという異変に気付くと、落ち着きを失って泣き始めた。
「りなちゃん! 大丈夫だよ。りーなーちゃん!」
とともちゃんにあやされても、一度気付いた恐怖はなかなか拭い取れない。りなちゃんの切実な訴えに応じて、私達は15分ほどの象乗りを楽しんだ後、またすぐにもとの広場に戻ることになった。象がゆっくりと昇り台の横に身を寄せて止まり、私達は象から降りた。
ガイド君の話によると象は一日200キロもの植物を食べる。それは近くの農村から約1000円で購入しており、ガイド君の日給の2倍のお金がかかっている。
「象の食事は高いけど、この村の一番の稼ぎ手だよ。」
と彼は言う。確かに、この象のりツアー代金が一人3000円である事を考えるとその通りだろう。
この後私達は、対岸にあるパク・オー洞窟に向かうことになった。ここは8世紀には既に僧侶の修行の場になったと言われており、今は何万体とも言われる石仏が収められている。河岸からエンジン付のボートに乗り、川面に揺られて約数分、船着場から左側へ進む石段を登ると上の洞窟への入り口に着いた。中には蝙蝠が住んでいると言う高さの見えない天井と、奥行きのわからない空間が広がり、石の壇上には何対もの石仏が暗闇の中に半分吸い込まれるようにして立っている。人々が祈りとともに捧げたオレンジ色の蝋燭は全て燃え尽き、燃え残った蝋が燭台の縁にこびりついている。私は思わず頭を垂れて、心の中で般若心経を唱えた。
右側の石段を登ったところにある下の洞窟は、鍾乳洞のような白色の岩で形成されており、岩の割れ目から指す日差しが空間を明るくしていた。その中で壁際から天井近くまで大小入り混じった石仏が並び、参拝者を静かに見下ろしている。岩が修行の場となるのは、西洋、東洋に共通する文化だろうか。
ルアンパバーンへの帰途、米から作ったお酒を作っている村を訪ねた。ライスワインは甘みが強く残ったどぶろく。ライスウィスキーは40度の米焼酎である。村には女性がスカーフや巻きスカートとして使うシンという布を売るお店もあった。ある店頭に飾ってあった赤色の幾何学模様を織り込んだシンに私は心惹かれた。根気強く値段交渉をして、600円にて購入。ともちゃんによると、この値段は地方の村ならでは、だと言う。ビエンチャンでは1枚2000円近くし、地元の人にとってシンは大変高価なものである。
ホテルへ帰り着いたのは午後2時、うだるような日中の暑さの最中だった。部屋で休むというマリベルさんと別れ、ともちゃんと私は川沿いのレストランに行った。カオ・ソーイ(肉味噌入り麺)と焼きそばをシェアして食べながら、ともちゃんは
「実はね、マリベルさんなんだけど、、。」
とため息をついた。
「せっかくラオスに滞在しているのに、自ら積極的に動こうとしないの。有名なお寺や博物館のことを言っても「そんなのあまり興味ないわ。(I am not that interested in.)」といって一蹴するんだよね。」
私は眉をひそめた。
「それじゃあ、マリベルさんは一体何をしたいの?」
「ラオス人の日常生活を見たいって言うの。私のラオス人の友達の家に行って食事をしたときは、楽しんでいたみたいだけど。」
「でも、日常生活を見るというなら、自分で寺院にでかけてそこで出会うお坊さんや、市場のおばちゃんと話すのもそうだと思うけど。」
「そうそう。その通りなの! でも彼女にはそういう考えが全くないみたいで、、。私が色々友達に連絡してお膳立てして、そのことを当然と思っているみたいで。」
「そうなんだ、、。それにしても、I am not that interested inっていうのは失礼極まりない言葉だね。」
「そうでしょう?! しかも何かにつけフィリピンと比較して、ラオスのほうが劣っているみたいなこと言うんだよね。ラオス人は英語ができないとか。」
「なにそれ。でも、それは当たり前だよね。フィリピンはアメリカの植民地だったし、ラオスはフランスの植民地だったんだから。」
「そう思うでしょ? でも私のつたない英語だと、なかなか上手いこと言い返せなくて。」
ともちゃんは頬杖をついた。
大学の先生という職業柄もあるのだろうか、自分のスタイルと自国に対してのプライドが異常に高く、しかし自分からは行動を起こさず、「そんなものには興味ないわ。」が口癖の困った観光客、マリベルさん。
「ごめんね。なんか彼女の愚痴になっちゃって。」
「いえいえ。でもそんな人と10日間も一緒に旅行するのは大変だね。」
マリベルさんは「I'm not interested in.」という言葉で無関心を装っているが、本当に無関心ならば、ラオスには来ないであろう。厄介なことに「その程度のものには、私関心がないわ。」という少々鼻高々の兆候が彼女にはあるらしい。
この後、私はともちゃんと別れて、一人でワット・マイ寺院へと行った。まだ夜のお勤めが始まる前で、私は一人本堂へ入り、金色の仏陀像の前でたたずんだ。その空間と時間の中で、私を見下ろす仏陀の目は、私の心を投影する鏡の役割を果たす。母のこと、祖父母のこと、ボルネオのこと、仕事のこと。過去を振り返り、過去を思い、そして今ここにいる自分を考える。私は手を合わせ一礼し、本堂を後にし、街中の探索へと出かけた。
ワット・マイ寺院の前の通りは、徐々にナイトマーケットのお店の準備が始まっていた。果物やお惣菜を売る屋台も出ている。ランブータン、マンゴー、パパイヤ、バナナ、スターフルーツと並ぶ中に1つ見慣れない茶色いものがあった。よく見ると蚕のさなぎである。地元の人は炒ったものを食べるという。
角を曲がり、ルアンパバーンで一番の高級ホテル、アマンタカの前を通り過ぎると、何かを熱心に手帳に描いている一人の白人男性がいた。後ろに回ってそっとのぞくと、それは風景のスケッチだった。
「上手ですね。(Nice picture!)」
振り返った彼は、ペンを止め、
「thanks.」
と笑顔になる。
ラオスを旅行中に好きなところでペンを取り、気ままに描きためたといういくつかのスケッチを彼は見せてくれた。ボールペンつで時間をかけて描かれた黒い線の町並みの描写はどこか不思議な温かみがある。
「僕は別に絵を習ったわけじゃないんだけど、ただ描くことが好きで、、。」
「それ、一番大切なことだと思います。(That's most important thing.)」
旅先にて絵を描く人に出会う。自分もペンを取ってみようかと思う。
ワット・ビスンナラートの境内を通り、T字路の突き当たりにあるHiveというカフェを併設している本屋に入った。漆黒の本棚にはラオスの文化や仏教に関する本が多く並び、奥のテーブルにはオーナーと思われる黒縁のめがねをかけた白人女性が座って本を読んでいる。
「こんにちわ、、。」
「いらっしゃいませ。何かお探しですか? (What can I do for you?)」
彼女は本から目を離してそういった。私は、このラオス在住歴が長そうな女性が仏教に造詣がありそうな気がして、
「すみません。ちょっとお尋ねしたいのですが、ラオスの仏像は皆、頭が尖っていますよね。あれ、どんな意味があるんですか?」
尋ねた。
私の絵 ラオスの仏像はこのような姿のものが多い。
「いい質問だわ。ちょっと待ってね。そういうことは私より、私のアシスタントの子の方が知っていそうよ。」
彼女は携帯を取り出し、親切にもその娘に電話して尋ねてくれた。
あの頭の部分は天を指しており、涅槃に行けるようにと言うことを意味しているという。
「日本の仏像にはないです。不思議ですね。」
「そういえば日本の仏陀は恰幅がいいわね。」
そういって彼女がパソコンで検索したのは、鎌倉の大仏だった。確かに鎌倉も東大寺も日本の仏陀は恰幅が良い。実在の仏陀はどうだったのだろう。ある国にある彫刻形式が定着する過程にはどんな要因があるのだろうか。
「話は変わるけど、今日の夜、この本屋の隣のHive Cafeでラオスの山岳民族の伝統衣装のファッションショーをやるの。興味があったら是非見に来てくださいな。」
と彼女は言った。
山岳民族とファッションショー?
「なんか不思議な組み合わせですね。友人がいますので誘ってみます。」
その後、ルアンパバーンの町を一望できるプーシーという小丘に登り、大勢の観光客と一緒に夕暮れの風景を眺めた。そしてメコン川の方に下り、ナイトマーケットで買い物中のともちゃんとマリベルさんに合流した。Hive Cafeでのファッションショーのことを話すとマリベルさんは例のごとく「I'm not interested in,,」だったが、説得の末、私と一緒に来ることになり、ともちゃんは買い物が終わってからりなちゃんと一緒に来るということになった。
二人が到着した時には既に何人かの観光客がテーブル席に座っており、前には照明が灯されたL字型の舞台が設置された。ポップミュージックがかかっていた。山岳民族という雰囲気からはかけ離れている。ピザとビールを注文してしばらく待っていると、本屋のオーナーの女性が現れ、ショーの説明を兼ねてそれぞれのテーブルのお客さんに話しかけ始めた。私たちのテーブルに来る前にちょうどともちゃんが到着し、彼女は笑顔で歓迎の意を表した。
「よく来てくださったわね。私たちは長年かけて80着以上の民族衣装を集めたの。今夜のショーでは地元の男の子や女の子がモデルとなってその衣装を見せます。どうぞ楽しんでいってくださいね。」
音楽が変わり、ショーの始まりとなった。
鮮やかなライトに照らされて、民族衣装を着た6人の男女が舞台に登場しその中央に歩いてきて並んで立った。そして彼らは半身になって笑顔を作った。身を反転し背中を見せて、舞台後方へと歩く。と同時に別の民族衣装を着た女性たちが現れ、舞台の中心に歩み出る。
アカ族、モン族、カム族、タイダム族、と部族ごとにショーは進む。白い布でできた大きな頭への被り物と白いドレスの花嫁衣裳。同じく白い衣装に身を包んだ男性に手をとられて、2人は舞台の中央で回転する。
黒い膝丈までのスカートは、農作業をする女性たちが着る民族衣装でもある。彼女たちは竹で編んだ背負子を持って歩き、回転する。
私たちは目も心も奪われた。そのショーはパリコレのようにプロフェッショナルであり、かつ民族衣装の美しさを余すところなく見せていた。消え行く民族衣装という概念が覆った気がした。
「こんなショー、ラオスで見たことないよ! 見つけてくれてありがとう!」
とともちゃんは大感激。マリベルさんも
「いいわね。なかなかおもしろいわ。(It's good, quite interesting)」
とまあまあ満足な様子。
ショーが終わったあと、再度オーナーの女性が「楽しかったですか?」と話しかけてきた。
「すばらしかったです。このショーは、あなたがプロデュースしたのですか?」
「私じゃなくて、ファッション関係のことをしている娘なの。でも私も若いころは少しファッションの仕事をしていたわ。」
フランス人である2人はラオスに移住してその民族衣装の奥深さに見せられ、数年前からこのショーを始めたという。フランス人が持つ天性の美的探究心と、悠久の時間をかけてラオスの民族衣装に織り込まれた美。その2つの見事な融合。
フュージョンアート。
それが、私とともちゃんの帰り道のキーワードになった。
5月9日
翌朝は托鉢を見に行くために皆で朝早くおきた。ホテルを出て角を曲がると、そこには昨日の朝と全く同じ光景があった。地元の人々は供物をささげるために路傍にたたずみ、道の向こうからは、列になった僧侶たちがゆっくりと歩いてくる。
1893年以降、フランスはラオスを植民地ではなく保護領として扱った。海に面したベトナムと比べて、内陸国であり奥深い山岳地帯に覆われたラオスにはフランスの積極的な開発・統治政策は行われなかった。また攻撃性や暴動性がないと判断された仏教も王家とともに存続が許され、それが今日まで引き継がれている。
ここで私は嫌なものに出会った。昨日の朝お金を請求してきたおばちゃんが、今朝もここにいたのである。僧侶の列が過ぎ去った後で、彼女は大股で私に歩み寄り、何か文句を言い始めた。ともちゃんが間に割って入って話しを聞く。
「彼女は昨日3籠分も托鉢をした。だから500円払え。」
という。目が点である。私の肩を押さえて托鉢を続けさせたのはおばちゃんではないか。ともちゃんが
「彼女はラオス語がわからなかったから。托鉢も初めてだったから。」
と説明し、100円のお金を払うことで決着をつけた。それにしても、観光客がいるがゆえに、托鉢が地元の人々の荒稼ぎの方法になっているのは悲しい。
私たちは僧侶たちの列を追って、ルアンパバーンで一番大きいワット・シェントーン寺院に向かった。
墓所として建設された古い歴史を持ち、本堂を覆う金色の湾曲した7枚の屋根、外壁を取り巻くように描かれたラーマーヤナの物語絵、そして聖水の出るガネーシャの胸像が有名である。
しかし仏教寺院なのに、なぜ、ヒンドゥーの神であるガネーシャがまつられているのだろう。
ラオスの仏教はカンボジア・クメール王朝の流れを汲む。その象徴であるアンコールワット寺院は12世紀に送検された時はヒンドゥー教の寺院だったが、16世紀には仏教寺院に改修された。宗教の繁栄と衰退、その歴史的変遷の影響を受けながらラオスの仏教も形成されてきた。そのため、ラオスの仏教寺院は、仏教とヒンドゥーの要素が混在している。という風に、日本人の私には見える。
しかし、それでは逆に、日本の仏教はどうなのだろうか。
混ざり気のない、純粋な仏教なのだろうか。
日本のお寺を思い出してみる。
お寺への入り口となる門の両脇に立つ金剛力士像は、サンスクリット語でヴァアジュラダラという仏法の守護神。そういえば日本には、仏法の守護神と呼ばれる神様がとても多い。四天王、大黒天、吉祥天、摩利支天、鬼子母神、十二神将、雷神・風神。
手水場では、龍頭から水が出ている。日本のお寺では龍は、手水場、梵鐘の取っ手、本堂の壁の彫刻として存在を現す。しかしこれらには仏教との明確な関わりはなく、中国から伝わってきた龍神信仰が神社仏閣の建築の中に自然と取り入れられたものだろう。
どこのラオスの寺院にもあった、ナーガがブッダを背後から守っている像は、瞑想中のブッダをムチリンダ竜王が風雨から守ったという伝説に由来している。
仏陀にまつわる有名な逸話であるにも関わらず、日本の寺にはこの彫刻は皆無である。彫像の対象となるかどうかは、その国にその動物がよく見られるかどうかに関係しているのではないだろうか。日本には蛇はいるが、その数と多様性は熱帯の国々とは比較にならないだろうし、日本には象はいない。
本堂にはご本尊が祭られているが、日本ではこのご本尊がこれまた多種多様である。
釈迦如来、大日如来、阿弥陀如来、薬師如来を始めとする如来様。
普賢菩薩、観世音菩薩、虚空蔵菩薩、地蔵菩薩、勢至菩薩、弥勒菩薩、文殊菩薩を始めとする諸菩薩。大日如来の変化である不動明王、その眷属である八大童子。観音様はさらに細かく、千手観音、十一面観音などとなる。
ラオスでは仏陀像だけであった。
東南アジアに伝わった上座部仏教は、伝統的な戒律を守った出家者たちによる原始仏教の側面を強く持つ。その中では信仰の対象は、悟りに至ったゴータマ・ブッダその人であった。
それとは対照的に、日本に伝わってきた大乗仏教は、伝統的な戒律の厳しい遵守に疑問を持ち、全ての人を含めた衆生救済、利他主義の重要性を認識した仏教の一派である。その主たる経典は、般若経、法華経、阿含経、涅槃経などであり、伝播の過程で解釈の仕方などが変化しながら、数百年かけて成立したと言われている。その間に信仰対象としての釈尊も、病気治癒には薬師如来、来世成仏には阿弥陀如来、世俗救済には地蔵菩薩、という風に細分化していったのではないか。ご本尊がこのように多種多様なのは、大乗仏教ゆえの特徴と思うのは、私だけだろうか。
お堂の奥で行われているご祈祷。護摩壇の上部には、注連縄と木綿が吊るされている。これらは神聖な場所の境界を示す日本古来のもので、仏教由来のものではない。しかし仏教の伝来とともにこの風習はお寺にも取り入れられた。
「稲成り」を祈願して神社の前に屹立するお稲荷さんのキツネの像は、日本固有の動物崇拝に由来している。厳密にはお稲荷さんはお寺にはなく、仏教とは縁がないが、日本では大きなお寺の境内の中に神社があったり、神社と寺が隣接していたりして、もし外国の人が見れば「日本の寺には何故かキツネの像がたくさんある。」と思うだろう。
日光の三猿。「見ざる、言わざる、聞かざる」は、天台宗の「不見、不聞、不言」という考え方に端を発するといわれるが、これが猿の彫刻の形を取ったのは「さる」の語呂合わせがよかったことと、猿という動物が日本人に身近であったためではないだろうか。もし日本に象がたくさん住んでいれば、「見ないぞう、言わないぞう、聞かないぞう」という三象という彫刻が祀られるようになっていたかもしれない。
また、日本のお寺には多くのご神木がある。ブッダへの祈りを捧げるお寺の境内に、神様が宿った木があり、それには注連縄と木綿が結ばれており、人々は手を合わせて拝む。こうして見てみると、日本の仏教とは何なのだろうか。
その他、神社仏閣に祀られているもの。仁王像。天狗。道祖神。猿田彦。庚申塚。七福神。なで牛。力石。


もし、ラオスの僧達が日本の神社仏閣を訪れたら、それこそ、仏教、神道、道教、動物崇拝、植物崇拝などなど、様々な要素が複雑に入り混ざった不思議な仏教と感じるに違いない。
仏教の特徴として寛容であることが言われる。伝播して行く国に元々あった自然崇拝を包含する形で仏教は浸透していった。ラオスの仏教にも日本の仏教にも、寛容性が見られることが共通点なのかもしれない。
話をルアンパバーンのワット・シェントーンに戻す。
7時を過ぎて徐々に境内には観光客の数が増え始めた。ホテルへ戻るという2人と別れて、私は街中をランニングしに行った。
川を渡って西南方向に向かい、ワット・タートルアンという寺院の前に着いた。中では、少年僧らが境内の掃除をしているところだった。橙色の袈裟を身にまとい、静かに竹箒を動かす素足の彼らたちを、常緑の大樹がその影で見守っている。私は、まだ木窓が閉じたままの薄暗い堂の中に入り、わずかに差し込む日の光でぼんやりと輝く仏陀像の前に座った。
しばらく眼をつぶって合唱していると、後から素足の気配があり、
「Hello,,」
ぎこちない英語の呼びかけに、私は振り返った。少年僧の一人がいつのまにか、本堂に足を踏み入れていた。
「Hello. Was it OK for me to enter?(こんにちわ。入っても大丈夫でしたか?)」
彼は頷いて、微笑んで尋ねた。
「Where are you from?(どこからですか?)」
「From Japan. So,,you live here as munk?(日本からです。あなたは、僧侶でここに住んでいるんですか?)」
そんな会話から私たちはしばらくお互いに質問を交わした。彼は実家の農村部から、僧侶になるためにルアンパバーンに出てきた。今はここに住みつつ、日中はハイスクールに通っているという。
「へー、そんな学生をかねているお坊さんもいるんですか。」
「たくさんいますよ。僧侶になると学費が安くて済むんです。僕も高校を卒業したら僧侶をやめて、コンピューターの仕事に就こうと考えています。でもそのまま僧侶を続ける人もいます。」
「学費っていくらなんですか? 安いって言っても、僧侶で学生だとお金を稼ぐことはできないでしょう?」
「1年で1500円です。人からご寄付してもらったものを、僕は貯めています。」
私はランニング姿でお金を持っていなかったことを後悔した。
「そっか、、。いい仕事が見つかるといいね。願ってます。」
握手をしようとして手を差し出すと、彼は一瞬肩を震わせて言った。
「I can't touch you.(僕はあなたに触ることができません。)」
私は息を飲んだ。あわてて右手を引っ込めて
「Sorry, sorry.(ごめんなさい。)」
といいながら、少し下がって正座し直した。
目の前に座る、僧衣をまとった少年の純粋すぎる禁欲的態度。私は強く胸を打たれた。しかも彼の発した言葉からは、不思議なことに、修行の妨げになる女性という負の概念ではなく、僧として触れてはならない女性の優しさ、美しさという温かみが感じられた。
私は両手を胸の前で合わせて、彼の学業成就を祈り、本堂を後にしてまた走り始めた。
ホテルに戻り、昨日と同じく河岸のオープンテラスで朝食をとりながらともちゃんとマリベルさんの今日の予定を聞いた。2人は夕方の飛行機でビエンチャンに帰るが、その前にどこにいくかはまだ決めていない。
「私はしばらくりなちゃんとホテルでゆっくりしていようかな、、。だからよかったら2人で、、。」
というともちゃんの意を汲んで、私はマリベルさんに、ボートに乗ってメコン対岸の集落を訪ねに行くのはどうかと誘った。しかし彼女は、
「そんなの興味ないわ。」
と肩をすくめながら言う。本当に興味がないとしても、もう少し別の言い方があるだろう。
朝食後、私は2人と別れて、単独で渡し船乗り場へと向かった。少しお腹の出たおじさんと交渉し、対岸での滞在時間3時間、往復の代金30000キップ(300円)という条件で出発してもらうことになった。
赤茶色の川面をエンジンの音が切って進む。100メートルもない川幅なので、すぐ対岸に到着し、私は土手のぬかるみにはまらないように舟を降りた。
「じゃあ、3時間後にお願いしますね!」
「ああ、3時間後だ。」
船頭のおじさんに念を押した後、土手を登って集落のほうへと向かった。ここはメコンの右岸に当たる。中心部である左岸がここ近年大きく開発されているのに対し、右岸は川に沿って集落を貫く道路が1本あるのみで、それも歩いて行くとすぐに未舗装になった。常緑の巨樹の中を軽快に歩いて行く自分がいる。途中地元の男の人たちが開墾作業をしている横を通り、小一時間ほど歩いただろうか、行き止まりになった所が静かな寺院の境内だった。
僧房があり、本堂があり、いくつかの仏陀像があった。川に面した木陰の中では、オレンジ色の袈裟を着た僧侶と、Gパンをはいた男性が楽しそうに会話している。私は側に行って声をかけた。振り向いた2人の表情はとても穏やかで、
「こんにちわ。あれ、下の船着き場から登ってきたんですか?」
と僧侶の彼が真下の河岸を指した。
「ううん。集落の方の船着き場です。ずっと歩いて。」
「それだと大分かかったでしょう。どうぞ座ってください。」
切り株に座っていた2人は、間にある平石に腰掛けるよう、私に勧めた。
「この真下にも船着き場があるんですか?」
「はい。彼は今日そこから来ましたよ。」
僧侶の彼は、そういってGパンの彼を見た。
2人は数年前にタイの寺院で僧生活をともにした友人同士だという。Gパンの彼は短期間で僧を止め、僧侶の彼はそのまま修行を続けた。
「僕は僧生活は1ヶ月でもう十分だと思ってやめてしまいました。今は教育関係のNPOで働いています。仕事でルアンパバーンに来たんです。」
「僕は瞑想するのが好きだったので、僧生活も気に入りました。父はルアンパバーンの中心にあるワットマイ寺院の住職で忙しくしていますが、僕は静かなほうが好きでこの寺院で生活しています。」
2人の話し方は、まるでメコンの流れのようにゆっくりとしてやわらかい。そして僧侶の彼は、まだ30代と若いながらも、10年を越えた修行生活がもたらす世俗から離脱した雰囲気と不思議な貫禄とを兼ね備えていた。
彼はタイで修行をしていたときの思い出を語ってくれた。1ヶ月近く野営をしながら山岳地帯を1000キロ歩く修行があった。恐かったのは、野生の象への遭遇。しかし、僧侶たるもの平常心を失い慌てふためくわけにはいかない。夜は火を炊き続けて象が近寄ってこれないようにし、日中は少しでも象から離れるために、皆我先にと競うように歩き、一行の歩くスピードがどんどん速くなったという。
「本当に怖かったんですよ。」
彼は当時を思い出して、静かに微笑む。
「住職をされているお父様は、今、おいくつですか? 引退とかってあるんですか?」
「いや、引退はないですよ。僧侶としての生活を続けて、その後は仏陀の息子となります。(He continues a life as a munk. After that he will be son of Buddha.)」
いつの間にか1時間経った。Gパンの彼と私には行かなければならない時刻が訪れた。旧友同士は別れを惜しむ。その2人に私は改めてお礼を言った。
境内を後にする前に切り株のあった場所を振り返った。僧侶の彼が結跏趺坐の姿勢をとって一人静かに瞑想していた。
船着き場に着く前に、見晴らしの良い丘の上にあるChomephet寺院(Wat Chomephet)を訪ねた。
建物は遥か昔に廃墟となった寺院だが、本堂の中に仏陀像の前にはここ数日のうちに生けられた花があった。遺構の上に腰を下ろし、メコン川をはさんで対岸の街中を見つめる。蒼空と入道雲の白、プー・シー丘陵の濃緑、そしてメコン川の赤茶色は、写真のように美しく、鮮やかに力強く瞼の裏に焼きついてくる。
集落の船着場には船頭のおじさんが迎えに来ており、私は勢いよく波を切るボートに乗ってルアンパバーンの街中に戻った。
ホテルのフロントでは、ともちゃんがおいしいカオ・ソーイのお店を尋ねており、4人でトゥクトゥクに乗りそこへ向かう。ところが、さすが人気店、今日の分はすべて終わりましたと言われ、隣にあったお店へと入る。カオ・ソーイ通のともちゃんにとっては肉味噌の味がいまいちだったらしいが、このお店には経営者の娘さんでちょうどりなちゃんと同い年ぐらいの女の子がいた。店内をとことこと歩き回る2人をお店のおばちゃんがまとめて見守ってくれる。ともちゃんはつかの間、子供の面倒から開放される。
「ラオスはこれがあるから、子連れでも旅行がしやすいんだよね。」
「わかる。インドネシアとかマレーシアでもこういう雰囲気あるよ。」
大家族ならではの、東南アジアの国々に共通したおおらかさ。
午後、一人ルアンパバーン博物館に行った。門からは椰子の木の並木が続き、右側には礼拝堂、左奥には円形の池がある。二階建の重厚な建物は、王家の人々が1975年、共産政権によってその地位を剥奪されるまで実際に生活をしており、後改装されて博物館として一般公開されるようになった。駆け足で回れば1時間ぐらいの展示内容であったが、時間があったのでメモ帳を手に、心引かれた仏像をゆっくりと描いたりしながら回った。
西暦900年頃、寺院創建時に貢献した人々の名前がラオス文字で刻まれた石碑。言語学的に変遷を重ねてはいるのだろうが、ラオス語は古い言語である。王家の子供達が身に着けて習ったというラーマヤーナ舞踏の衣装と仮面。なんと教養高い遊びであろう。
ホテルに戻った時、ともちゃんとマリベルさんは帰るための荷物のパッキングをしており、私も今夜は安宿に移動するので自分の分をザックに詰め込んだ。今度2人に会うのは、私が3泊4日の山岳トレッキングを終えてビエンチャンに帰る24日である。ナイトマーケットのお土産とりなちゃんを抱えてトゥクトゥクに乗り込んだ二人に、つかの間の別れを告げてお見送りする。
夕方5時近く。ルアンパバーンに1人になった私は、再度博物館の横のワット・マイ寺院に行った。境内で遊んでいた5〜6人の子供達はそのうちに家に帰り、その後、1人の僧侶が本堂の中の銅鑼を何回か大きく鳴らした。すると読経の本を持った僧侶達が本堂に集い始め、5時半にチャンティングが始まった。20人近くの老若混ざった僧侶達、その後ろに地元の女性が2人、そのさらに後ろに私は座った。女性の1人が振り返り、笑顔でそして小声で
「Do you like chanting? (チャンティングは好きですか?)」
「Yes.(はい。好きです。)」
私も小声で答えた。
まるで合唱のようなラオス独特の読経は、いつの間にか、聞きほれてしまう。透明感のある旋律は、精神の奥底に浸透してくる浄化作用がある。
陶酔していた私は、いつしか読経が終わり、はじかれたように我に返った。最前列に座っていた住職と高弟たちは向きを変えて座りなおし、弟子の僧侶達に何かの問いかけを始めた。
禅問答のようなものだろうか。
少年僧の答えはとんちでも聞いているのか、何人かが笑う。年配の弟子の答えには、皆声を傾ける。そして、それらを総括するように高弟の1人が説法をする。
その問答の時間が終わり、僧等、そして私達も仏陀像に向かい黙礼した。そして夜のお勤めは終わりとなり、彼らはそれぞれに立ち、本堂を後にし始めた。先ほどの女性が振り返り、またニコリと笑顔をこぼす。私も思わず口元を緩ませ、
「すみません。あの、先ほどは何を話していたのでしょうか。」
尋ねた。
「今のお話は、私達はどういう風に身の回りにあるものを考えればいいかということでした。例えば、食べ物や、家や衣服やら、、。あ、もし良かったらお坊さんにもう一度説明してくださるように、お願いしましょうか?(It was about how we should consider things around us. For example food, house, cloths and so on. It was really nice talk. Well, if you want, I will ask a munk to explain it to you.)」
「いいんですか? もしお坊さんにお時間があれば、、。」
彼女は待っていてくださいねという風に笑い、駆け足で本堂を出て行き法話をしていた高弟に声をかけてくれた。
空に夕闇が落ちてくる中、境内のマンゴーの木の側に彼は立ち、私たち3人は取り巻くようにして座った。
「先ほど話したことですが、もう一度説明いたします。」
彼は完璧な英語で言う。
「あなたは日本からいらっしゃいましたか。」
「は、はいっ。」
かしこまって私は答える。
「日本とラオスでは、大乗仏教、上座部仏教という違いがあります。でも日本でも大半は仏教徒と聞いております。」
私はそうです、と頷いた。
「仏陀は悟りを開く前に、大変厳しい修行を体験しました。しかしあまりに極端な苦行は、彼に何の益ももたらしませんでした。王家の跡継ぎとして生まれ育った彼は極端に贅沢な暮らしにも益がないことを知っており、その2つの体験から中道という考え方をするようになりました。中間に、ほどほどに、という意味です。」
彼は私が理解しているのを確認してから、
「我々は生活しながら様々なものに負担をかけています。例えるならば、家を作るときは土を耕すために虫の居場所を奪い、木材を得るために木を切り、同時に森に住む動物達の住処を侵しています。食べ物や衣類でも同じです。そのことをいつも頭にとどめて考えなければなりません。」
と言った。
「仏陀は我々が生きていく上でそれらを用いることを禁じはしませんでした。しかし、何のためにそうして生きるのかを考えなければなりません。食べ物を食べるのは太るためではなく、衣類を身に着けるのは華美に着飾るためではありません。なぜ、我々は生きるのでしょう。他人に良きを施すためです。(we live for doing good for others)」
彼は、わかりやすくとても噛み砕いて説明してくださる。
「我々、僧が持っているものは、この袈裟3枚、托鉢壷、そしてわずかな筆記類です。人というものは感情に振られてすぐに大切なことを忘れてしまいます。だから、例えば日に一度、このことについて思いをめぐらすことが大切だと思います。」
彼の言葉は清水で、私の胸はその清水で満たされた。
「判っていただけたでしょうか。」
私は強く頷きながら、額が地面につくほど頭を下げ、感謝の意を表した。彼は脇に抱えていた本を持ち直して、尋ねた。
「あなたは、どのくらい旅行をされていますか?」
「10日間です。」
「そうですか。よい旅をしてください。」
彼は微笑み、そして一礼して、僧房のほうへ去って行った。少年僧が井戸端でオレンジ色の僧衣を洗っている。高弟の彼も、明日のために自分の僧衣を洗うのだろう。
横にいた女性はうれしそうに私を見据え、
「良かったです。それではお休みなさい。(I'm glad. Good night.)」
と言った。僧侶は夜のお勤めが終わると就寝し、朝は夜明け前に起きる。この信心深い女性は僧侶と起居をともにしているのだ、と私は知った。
群青色の星空が降りてきていた。境内を後にすると、私の後ろで静かに「今日」という門が閉まった。
その後、今夜宿泊予定のサヤナという安宿に行き、部屋に案内されて驚いた。地球の歩き方には男女別々のドミトリーと記載されているのに、男女一緒だったのである。ガタイのいい白人のお兄さんが気だるそうにベッドに寝ており、一抹の不安がよぎったが、今更新しい宿を探すのも面倒である。私は宿泊を覚悟し、何事もなく一夜を過ごせますように、そう願いながら割り当てられたベッドに荷物を置き、貴重品を持って街中に出かけた。
博物館、ワット・マイ寺院の前を通過し、細い路地への曲がり角にある屋台で私はチャーハンを注文した。すると、同年代と思われる女性が店内に入ってきて隣のテーブルに座った。中国出身の目の大きな美しい女性で、お互いに一人旅をしていることがわかった。
「以前は上海で外資系の会社に勤め、そこでまとまったお金を稼ぐことができました。そして上海からスタートして、中国南部、雲南、チベット、その後ミャンマー、タイの北部を旅して、ラオスに入りました。もう2年近くになります。」
私は目を見張った。予期せぬ旅の達人である。チベットではボランティアと言う形で中国語(マンダリン)を教える仕事に就き、6ヶ月をそこで過ごした。とてつもなく美しい、忘れ難い大地だという。
夕飯を済ませた後、2人でナイトマーケットを一緒に歩いたが、彼女はあまり興味を示さない。長期の旅は、彼女を観光客向けの品物には惹かれない「旅人」にしているのだろう、と私は思った。
先刻の不安とは裏腹に、ドミトリーのベッドは意外と快適で、私はぐっすりと安眠することができた。
5月20日
ルアンパバーンですごす最後の朝を、ワット・マイ寺院の托鉢を見たり、サヤナの前のワット・ホシアン寺院、プー・シー丘陵の横のワット・シープッタバート寺院を散策したりして私は過ごした。7時過ぎにドミトリーの部屋を出て、市場にあった店頭で湯気を立てて麺をゆでているカオ・ソーイのお店に入った。目の前でおばちゃんの手はせわしなく動き、野菜を切って、海老の腸を取って、その合間に茹で上がった麺を器にざっと移す。肉味噌、コリアンダーがその上に散らされ、ゆでたもやしとインゲンが副菜としてつく。50円のカオ・ソーイからエネルギーをもらい、私はグリーンディスカバリーのオフィスに向かった。
今日から2泊4日の山岳民族の村を訪ねるツアーに参加する。ガイドのマン君は、しっかりした肩幅を持った人懐っこい笑顔のお兄さんで、私は帽子をとって挨拶し、これから3日間のトレッキングの無事を祈って彼と握手をした。
グリーンディスカバリーのバンに乗って幹線道路である13号線を北上し、約1時間後にホワイロー村という小さな集落に到着した。外で遊んでいた子供達は、珍しい車の到着を知ってさっと柱の影に隠れたが、そのうち顔を出して様子を伺う。私がラオス語の旅の指差し会話帳を見せると、そのイラストを1ページずつ楽しそうに眺め始めた。
集落の近傍に、材として使われるティークツリー(Lamiaceae Tectona grandis)の林があった。マン君が葉を取って手で揉むとそれはすぐに紅くなった。
「昔は村の人はこれを口紅に使ったんだよ。」
興味深い。日本での紅花然り。
今日から2日間かけて、モン族とカム族の住む村々を訪ね歩く。モン族は中国南部からの民族で東アジア系の顔立ち、カム族はカンボジアから渡ってきた民族で南方系の顔をしている。ラオスには50以上もの少数民族がいるが、600万の人口の9割はラオ族が占めている。
炎天下の中、農閑期の畑地を歩き、汗が一気に噴出してくる。辺りには水田が多くあり、田植えが始まるのは6月、収穫は11月ごろ。日本と同様に一年に一度しか作ることができない。焼畑も見られるが、焦げた大地に乾季の太陽が降り注ぎ、さらに灼熱とした感じが漂ってくる。その中を歩きながら、私は色んなことを尋ねた。
マン君の父はダイダム族、母はカム族の人で、2人は農作物を売りに市場に出かけていたときに知り合い、結婚した。昔は同族間での結婚が当然だったが、道路や行商の発達に伴い、他民族間、さらには外国人との結婚のケースも増えている。父方の族を受け継ぐのが一般的で、マン君の持っているIDにはタイダム族と記載されている。
彼は教育の専門学校に学び、その後自分の生まれ育った村で小学生にラオ語を教えた。と同時にガイドとなるための英語を学び、4年前からグリーンディスカバリーで働き始めた。彼は天性の語学能力の持ち主で、ラオ語、英語、そして今はカム語とモン語もしゃべれるという。
1時間ほど歩いて到着した集落はモン族のバンファーファウン村だった。数人の小さい子供に、数匹の犬や豚。想像以上にひっそりとして人気がなかったのは、日中はほとんどの村人が畑に出て作業をしているためだった。マン君が、村人が通常使うという石臼を見せてくれる。かなり大型で大人2人が一緒になって回すという。
ここからさらに奥にある次の村を目指して歩き始めた。標高を稼ぐにつれて、遠方まで続く山脈があらわになり、急斜面に切り開かれた耕作地の真ん中には休憩のための掘っ立て小屋がある。休憩時に私は尋ねた。
「さっきの村のモン族は、ベトナム戦争で民族分断の憂き目にあったあのモン族だよね?」
「そうだよ。」
彼はリュックからペットボトルを取り出して言った。
モン族は、古来から中国南部、ミャンマー、タイ、ラオス、ベトナムの北部に住む山岳少数民族である。しかしその強靭な体力と山岳地帯における土地勘を買われて、フランス・アメリカの軍隊から訓練を受け、モン族特殊部隊(HSGU)としてベトナム戦争に参戦した。約5年に及ぶ東西両陣営の殺戮は、ベトナム戦争終結後ラオスが共産主義国家となった後も深い悲しみを伴う問題を残した。同一民族であるにも関わらず、政府側と反政府ゲリラ勢力に別れて生きることを彼らは余儀なくされた。今でもラオス国内には、HSGUの残党がゲリラ活動を続けている。そして政府はこの残党の一掃を最重要課題としている。
「ゲリラ活動のためにアメリカ側から資金が回っているといううわさもある。10年ぐらい前まではビエンチャンールアンパバーン間の高速バスが狙撃されることもあった。」
「本当?」
私は今回そのバスに乗っている。
「もう今はだいぶ安全になった。それでたくさんの観光客もラオスに来るようになったんだ。」
「マン君はやっぱり、アメリカ、嫌い?だよね。」
「好きじゃないけど、、何もいえない。今は経済開放でアメリカのものも色々入っているし。アメリカの観光客も来るしさ!」
彼は半分冗談で言った。
50メートルほど標高を稼いだところに次の集落はあった。小高い丘の上に小学校があり、その東側がモン族、西側がカム族の村となっている。両方の村の子供達がこの学校に通い、先生は片言のカム語、モン語を交えながら、ラオス語で授業するという。2言語混在の授業、一体全体、成り立つのだろうか?
「そりゃあ大変だよ。でも読み書きを勉強できることが幸せだ。戦争の時は学校なんてなかったから。」
その言葉に胸が詰まる。
小学校から、約200軒近い家のあるカム族のバンモッチョン村へと下った。家々は、竹で編まれた壁にヤシの葉で葺いた屋根を乗せており、村の広場には共同水道やトイレがある。発電機と電気を持っている裕福なうちも2,4軒あり、グリーンディスカバリーのツアー客は、順番にそれらのうちに宿泊させてもらう。マン君が「今日お世話になる家だよ。」と言ってある家の軒下に入り、玄関先にいた青いスカートの女の子に声をかけた。彼女はさっと立ち上がり、私を手招きして部屋の中に入った。その部屋は高床式の寝床で、板の間の上には0人分ぐらいの布団、そして蚊帳がぶら下げてあった。
大人たちはまだ畑から帰っておらず、村の真ん中の広場では子供達が鬼ごっこをして遊んでいた。私はそこへ行って軒下へ座り、折り紙を取り出した。突然の珍客に子供達は鬼ごっこをやめ、一気に私のところに駆け寄ってくる。彼らに囲まれ気分はまるでNHKののっぽさん。
「いい? 見ててね。」
私は青色の折り紙でまずは鶴を折り始めた。三角、四角、菱形と細くなり、頭、尾ができ両羽を広げて鶴の完成。子供らは感嘆の声を上げ、その目はきらきらと光る。1人の女の子が「ちょうだい。」と手を出し、彼女の手のひらにその鶴を乗せると、他の子供達も一斉に「お願い」「お願い」と手を出し始めた。いつしか、周りには小さい赤ちゃんを抱いたお母さんや高齢の人たちも集まり始め、私は折り紙お姉さんと化した。バラ、風船、パタパタ鶴。折り紙という芸術は初めて見ると、ただの1枚の紙から立体的なものが生まれるその不思議さに圧巻されるだろう。
2時間ほど折り続け、肩の凝った私は伸びをしながら
「ごめんねー! もう疲れちゃったよ!」
と日本語で言った。彼らもその意味を解したらしい。私は手を振って今日泊まる家へと帰り、土間から上がった板の間にしばし横になった。
おきると、マン君が早めの夕飯を作ってくれていた。炊き立てのもち米(カオ・ニャイ)とトマト風味のさばの缶詰を温めたもの。山での食事みたいである。
家から少し離れた家の前では、数人の男性がふいごを使って作業をしていた。
ふいごで酸素を送り火力を強め、農具の金属部分を熱する。
それを水で冷やして、打つ。その繰り返し作業。この村は、町から遠い。農具も全て自前で修理、補修しなければならない。
今日歩いた道は、ダートであるが四駆の自動車ならかろうじて通れる道であった。その場合、町から色んな物資を運ぶことができ、村の生活はだんだんと便利になってゆく。政府の役人が視察に来て共同水道が整えられたのも2、2年前で、以前は川まで水を汲みに行く必要があり、生活はとても大変だったという。
5時過ぎに、トラクターに乗って父、母、そして青いスカートの女の子の兄、姉ら2人が家に帰ってきた。
炎天下での作業から疲労困憊して帰ってきた父親は、私を見てモン語でマン君に何か尋ねた。
「そうか。泊り客かい。」
そう父親の男性が言った気がした。母親は娘らと調理場に入りすぐに夕飯の支度に取り掛かる。息子はトラクターを家の前から別のところに運転していき、父親は農作業具を片付けている。誰も私の存在を気にかけない。
マン君によると、彼らは今日私が来ることを知らなかった。ツアーの人数が少ない時は、わざわざここまで来るのも大変だし、事前に知らせないという。
もち米に簡素な野菜スープという家族の夕飯が始まった。彼らは時々、何か農作業に関することだろうか、を口にしながら黙々と食べ、片付けが終わるとすぐに寝床に行ってしまった。
見事なシカトのされ方である。
遠来の旅行者にもう少し興味を示してくれることを期待していた私は、当てが外れて残念だった。しかし、これが彼らの真の日常なのだろう。年に一度の稲作でこの厳しい山岳地帯に生きていくためには、日々の農作業で一杯いっぱいなのだ。さらには、そんな彼らのぎりぎりの生活を、ガイドに連れられてふらりと見に来た外国人旅行者には友愛の情は沸かないのかも知れない。
「今日は週に度のテレビの日なんだよ。」
とマン君が言った。ここの村には軒だけテレビを所有している家があり、毎週日曜日夜8時から子供達が集まってドラマを見る。興味があったら行ってみたらいい、000キップ必要だよ。そう言われて、私はヘッドランプをつけて足元を照らし、約50メートルほど離れたテレビのある家まで歩いていった。
なけなしの1000キップを払って集まった子ども達はおよそ30人。そして8時30分にいよいよ、彼らが心待ちにしているドラマが始まった。内容はラオ語が理解できない私にも手に取るようにわかる、こてこてのラブストーリー。主人公の男女は本当は相思相愛なのだが、政略結婚相手の女性とその母親が2人の関係を許さない、というもの。子ども達はたった1つの電球が灯るくらい部屋の中で、そのドラマに夢中になっており、シーンに応じて「あ〜あ、、。」とか「やったー!」という声が飛び交う。その様子は、「三丁目の夕日」そのものであり、一昔前の日本を想像して私は胸が熱くなった。
5月2日
鶏の声によって朝起きると、部屋に取り残されていたのは私だけだった。竹壁は思ったよりも遮光度が強く、部屋の中は編目の隙間から差し込んでくる朝日によってわずかに明るいだけで、私は土間においてあるサンダルをはいて外に出た。隣の台所では、お母さんと娘が薪で火を炊いており、村人は顔を洗い身支度を整えて、畑へ行く準備をしていた。
昨日とは異なり、気だるそうに空にかかる厚い灰色の雲を見てマン君は言った。
「今日は雨が降るかも知れない。」
「うん。降りそうだね。」
その言葉通り、ちょうど出発する頃に小雨が降り出した。高台の学校まで登り、そこから昨日とは別の集落に下る。その広場で遊んでいた女の子の1人が、金色に近い髪の色をしていることに私は目を見張った。マン君によると、おそらくインドシナ戦争時のフランス兵の血が混ざっているという。
「結婚して、フランスとかアメリカに帰ったカップルもいるんだよね?」
「そういう人たちもいるし、そうじゃない人たちもいる。」
その集落を抜けると道は畑に向かって登りになった。止みそうにない雨に私が傘をさした後、しばらくしてマン君は路傍に生えていたバナナの葉を取りそれを傘代わりとした。両側に畑が広がり、所々にわらぶきの休憩小屋がある稜線を黙々と2人で進んでゆく。時々その小屋で休んでいる村人が「何が楽しくて雨の中こんなところを歩いているのだろうか。」という奇異な眼差しで私達を見る。観光客慣れしていないためか「ハロー」とか言って来る人はいない。目を向けるとさっと視線をそらす所は日本人と酷似している。
それにしても、雨は雨で、炎天下は炎天下で、この急傾斜の山地を切り開いての日々の農作業は、想像を絶するに違いない。
1時間ほど歩き、雨脚が強まる中、未舗装のダート道に隣接しているバンホンカー村についた。
昨夜の村よりもトタン屋根、コンクリート壁を持つ家の数が多い。わらぶき屋根は2年ごと、竹壁は4年ごとに交換しなければならず、それにはお金も時間も人手もかかる。お金のある村人達は、徐々に新しく便利な建材を求めるようになっている。
くすんだ茶色のわらぶき・竹壁の家が立ち並ぶ村の中で、ブルーのトタン屋根、薄ピンク色のコンクリート、ダークブラウンの木のドアを兼ね備えた家はとてもモダンで光って見えた。そのコントラストを見ていると村人の心理がとてもよく理解できる気がした。
例えば、多くのわらぶき・竹壁の家の集落がある。どこの集落にも徐々に道路が通じ、皆憧れのトタン屋根、コンクリート壁を持つようになる。どのくらいまで昔ながらの集落の数が減った時に、人々の間に「これは伝統的な家屋だから残そう。」という声が生まれてくるのだろうか。100分の1か、1000分の1か、10000分の1か。
このグリーンディスカバリーのツアーは少数山岳民族の村を訪ねることを謳っているが、数年後にはその名称を変更しなきゃいけないかもしれない。また1986年の経済開放政策以来、ベトナム、中国からの投資を得てメコン流域には複数のダム建設の計画が立ち始めた。カヤッキングのツアーができる川も少なくなるかも知れない。私はマン君からそんな話を聞いた。
この村を通過してダート道をしばらく行くと、大きなクボタのトラクターが木を倒して棚田を形成していた。
「このトラクターってさっきの村の人が所有しているの?」
「いや、今のトラクターは高くて村の人はとても買えない。13号線の近くに住んでいる人が持っているんで、ここまで来て作業をして、その作業費を村の人が払うんだ。」
ここから13号線まで車なら1時間ほどで着くが、6月から始まる3ヶ月の雨季の間は道路の一部が冠水し通行不可能となる。村人達はその間、陸稲の田植え・生育という忙しい時間を過ごし、集落の中に静かに留まる。
しばらく行くと、道路脇の小川の中に備え付けてある装置をマン君が指差した。それは川の流れが落ちるところにちょうどあり、今の水位の時期だけ使える水力発電機だった。しかし雨季のときは水没してしまうため取り外すという。
さらに10分ほど登るとわずかに沢音が聞こえてきた。何の標識もないけもの道のようなところをマン君は確認し「ここから降りて滝に行こう。」と言った。ほとんど人が通らない道は木が倒れ、その上に竹が生い茂っていたが、その間をくぐって降りて行くと、心地よい音を立てて水しぶきを立てている滝があった。私はここで、洋服のまま滝壺に使って少し泳ぎ、体を洗った。
ここから今日泊まるカム族のナサバン村までは後少しだという。村に近づくにつれて、右側にはここ近年できたという真新しい診療所、左側には小中学校があり、竹製の電柱には先ほどの水力発電機からの細い電線が通っている。
その奥には大きな村の広場があり、トタン屋根の家が数件、モーターバイクが数台見られた。やはり車の通れる道があるかないかは、物資の輸送、そして経済・生活水準に大きな違いをもたらす。
インスタントラーメンともち米とバナナというお昼を食べた後、私は折り紙を広げた。最初ははにかみながらこちらを見ていた3人組の女の子が、私の座っているテーブルに近寄ってくる。するとここからもそこからも、男の子や少年、少女が集まり始め、私の周りは子供達で一杯になった。
風船、パタパタ鶴、バラ。子どもらはつつが完成する度に目を見開いて歓声の声をあげる。それがなんともうれしくて楽しく折り続けていたのだが、何人かの子にあげたが最後、「私にも!」「僕にも!」という声が次から次に飛び交うようになってしまった。私は2時間ほど必死の折り紙お姉さんと化した。子供達は笑顔で折り紙を受け取り、大事そうに膝の上においたりする。だんだん肩が凝ってきたので、1人のお姉さんに身振り手振りで肩をマッサージしてくれと頼み、ようやく一段落着いたところで私は大きく伸びをした。
そして、子供達とは手を振って一旦お別れし、集落の裏に続く畑へと向かう山道を歩き始めた。小さな沢を2回渡渉すると、山の斜面を丹念に切り開いて作られた棚田が見え始め、さらにその先の山の稜線まで行ってみようと私は思った。焼畑の後にバナナやキャッサバが植えられた畑の中を、さんさんと熱帯の太陽が降り注ぐ下1人で登って行く。30分ほど登って到着した稜線の先には、遠方まで続く山岳耕作地が広がっていた。
しかしここで農業を基盤として生計を立てていくのは全く別物である。
同じ道を引き返して村に戻ると、そこでは男の子達がセパタクローで遊んでいた。竹で編んだボールを、頭と足だけを使って相手コートに打ち返す、マレーシア発祥の足バレーボールのようなスポーツである。最初は観戦していた私だが、そのうちに声をかけられて恐る恐るコートに入った。しかし、見るとやるでは大違い。足でのサーブは空振りか運よく蹴れても相手コートに入らず、跳んでくるボールは頭で受けようと構えつつ、でもタイミングが掴めず手を使ってバレーボールのように受けてしまう始末。でも村の男の子達は私の様子を、笑いながら見守ってくれ、30分ほどで、私はなんちゃってセパタクローを終了した。
しばらくすると、何十人かの子供たちが賑やかに村に帰ってきた。午後の部の授業が終わった小学生達で、村に入る手前のところに小学校があるという。
「行ってみたい?」
「是非!」
マン君は、私をその場所へ案内してくれた。
きれいに整地されたグラウンドの端に、村にあった家屋と同じつくりの校舎が2棟たたずむ。つい先程までここで子供たちが元気に遊んでいたことを思うと少し寂しい感じがしたが、就学時間中に訪ねると子供たちが勉強にならなくなることを懸念して、マン君は立ち寄らなかったのだろう。
校舎の中は、竹で編まれた壁でいくつかの教室に区切られ、中には黒板があった。その横には世界地図が掲げられ、地面の上にじかに机と椅子が並ぶ。
来週は学期末のテスト期間で、その後3ヶ月間は学校は休みとなる。その期間はちょうど乾季???で子供たちは畑の手伝いをする。
だんだんと日は傾いてきたが、まだ夜までには時間がある。私は、縁側にたくさんの村人が腰掛けている家を描いたり、また子供達にせがまれて折り紙を折ったりして時間を過ごした。
夜になり、まだ若き20〜30代のこの村の小中学校の先生ら4人と一緒に夕飯を食べることになった。現在、発展途上中にあるラオスは少数山岳民族を含む全ての児童への教育、特に公用語としてのラオス語の普及を急務としている。
彼らとビールを飲みながら、私はマン君に通訳になってもらい彼らのことをいろいろと尋ねた。4人のうち若い女性2人は、教員免許を取得後初めての勤務先がこの村で、英語と自然科学を教えている。ラオ族出身の彼らは、最初モン語がわからなかったが、今はそれを覚えてモン語とラオス語の両方を使って授業をこなしている。ここでの勤務は3年間で、2回目は別の学校で3年間、その後は勤務先や期間について希望を出すことができる。別の2人は30代の新婚のカップル。この村が3回目の勤務地で長期間ここに勤める予定だという。
マン君によるとこの村に日本人が来たのは初めてで、その人が村の学校の先生達と何か話をしているのはとても珍しいらしく、さっき一緒にセパタクローをした男の子たち、折り紙をした女の子たちが我々を遠巻きに眺めている。彼らが大人になる頃は、ラオスは大きく経済発展し、山岳集落の人たちも都心部に行って働く人が増えるだろう。
「私たちが小さかった頃はまだ村人はモン語をしゃべっていて、学校の先生がまず言葉を覚えるのに苦労したんだよ。」
「えー。そんな時代があったの?」
次世代の子ども達との、彼らの会話を想像してみる。
夜は、昨日と同じ高床式の部屋に蚊帳を吊って布団を敷いた。隣の家では、村の男の人たちが夜遅くまで熱心に何かを話していて、竹壁を通してぼんやりと聞こえてくる話し声が私は妙に気にかかった。
5月22日
夜中には雨は降らなかった。今朝の空もまずまずの状態で
「予定通り、難しいルートを行こう。」
マン君は言った。遠方に見える岩峰のわきを巻くようにして越え、小さな村を通り、そこから山道を下り13号線に戻るという。もち米とゆで卵という朝ごはんを食べて私たちは出発した。
マン君によると昨晩の会合は、今ヶ月間のみ畑仕事を手伝いに来ている他村の人々の給料についてで、長時間の話し合いの結果日250円ということで決着がついた。あの炎天下の作業でその値段かと感じたが、20日で0500円と公務員の初任給の約2倍になり、そんなに悪くはないのかもしれない。ちなみに私が宿泊した家には400円、通過した村には通行料として00円を払うという。
いつしか道は滅多に人も通らないけもの道となり、竹やぶをこぎ、するどい棘のあるバラ科の植物に気をつけながら急登を行くようになった。しかしそれも小一時間で一段落付き、岩峰がよく見える峠の上で私たちは休んだ。
「この岩山って誰か登ったことあるのかな?」
「いや、誰もないよ。こんな急な場所。」
マン君は笑った。確かに急峻ではある。しかしクライマーがハーケン、ボルトを打ち込んでザイルを組めば、すぐに到達できるピークだろう。おそらくラオスには未登攀の処女峰が数多く存在する。しかしそれらの峰々は、クライマーの登攀対象になるよりは、荒らされることなく静かに地元の聖山として聳え立っているのが幸せかもしれない。
そこからすぐの地点に2家族が住むというモン族のモッモエウン村はあった。村の広場には、牛、ヤギ、鶏が闊歩し、椰子の葉の屋根、竹で編まれた壁の家が並ぶ。
今までの村は四駆やバイクで到達することができたが、この村は本当の僻地にあり徒歩でしか来ることができない。電気はなく火は薪。水も近くの沢まで降りて汲みに行く。
「学校は?」
「この村の子供たちは学校には通っていない。でも近いうちに、村全体がもっと13号線に近い大きな村に移住する予定があるんだ。あまりにここは僻地だからね。」
私は、軒下にて遊んでいる子供たちに目をやった。穴の開いたTシャツ、裾がほつれているスカートやズボンをはき、足は裸足で、でも笑顔は屈託ない。ある男の子はカワセミのような青色の羽の鳥をカゴに入れて遊んでいる。マン君が頼むと、老父がジャックフルーツを鉈で割って出してくれた。それは甘くてとてもおいしかったが、この村の近い将来のことを思うと、せつない苦々しい味を感じずにはいられなかった。
この村を後にして15分ほど進むと、突如展望が開け、遥かかなたに13号線が光っているのが細く見えた。
これから道は焼畑や水田の間を縫うようにして下り、最終的に13号線に到達する。推定水平距離4〜5キロ、標高差1000メートル。道はすぐに急勾配になり、どこかから話し声とカランコロロンという愛らしい鈴の音が聞こえてきた。
その声の主は、荷運び用の山羊を連れたバーポン村の人々だった。彼らは農作物を売るために早朝村を立ち、その仕事を終えてまた村に戻るところだったが、市場で買った塩、衣類、鍋や傘などの生活用品があるために空身ではなかった。一人一人が20キロはありそうな荷を背負い、山羊は両方の背に荷を括られた状態で、苦しそうに首の鈴を鳴らしながら一歩一歩登ってくる。彼らは額に汗を流しながら山羊の手綱をしっかり握り、すれ違いざまに笑顔で会釈して上へ上へと登っていった。
日本の山岳地帯に当てはめると、南アルプス北岳山頂周辺で米や野菜を作り、週に〜2回それら農作物20キロを背負って広河原まで降り、そこで塩や洋服など必要品を買って再度20キロを背負って山頂まで帰るといった感じだろうか。帰った家には、電気、ガス、水道はなく、天気のいい日にヘリコプターが飛んでくることもない。
だいぶ山麓が近くなり、お昼を取るために畑の中の椰子で葺かれた東屋へ入った。マン君はバナナの葉を折って作った器にトマトのサバ缶を開け、昨夜泊まった家からもらったもち米を用意してくれた。
「野菜がほしい。」
という思いが、この3日間、私の頭を強く掠める。携行しなければならないお昼は別として、朝も夜も野菜がほとんどなかったのは今が乾季だからだろうか。
何はともあれそのお昼を終え、今日の最後の行程である13号線までの山道を歩き始めると、徐々に村人と行き交うようになった。さすがに幹線道路に面しているだけあって、畑を囲う柵や家の作りや農耕機械が今までの村に比べてはるかに近代的である。そして村を通り抜けると、13号線の道路脇にはグリーンディスカバリーの四駆車が既に待機していた。車はすぐに出発し、パートゥーン岩峰の姿を見たり、うとうとしているうちに1時間たち、ルアンパバーンに到着した。
グリーンディスカバリーのオフィスで、私はシャワーを貸してもらった。いくら自然の滝や共同水道がありがたくても、石鹸の使えるシャワーにはかなわない。私は丹念に体を洗って2日分の汗を流し、きれいなTシャツと短パンに着替えた。そしてマン君にお礼を言ってオフィスにザックを置かせてもらい、熱帯の太陽が降り注ぐ中、町の中へ散歩に出かけた。
木陰を求めて入ったワット・シープッタバート寺院の境内は、巨木と本堂が屹立し、穏やかな静寂に包まれていた。階段の上の建物のベランダにはオレンジ色の僧衣が2,2着干してあり、それが僧房であることがわかる。
僧が所有しているものは、僧衣2着と托鉢壷とわずかな筆記用具。物質的には極めて質素であるが、それが逆に、情報過多社会の中に生きている都会人には、この上ない豊かさと深遠さを持った形であるようにも思える。
このお寺をお参りした後、私は再度Hive cafeの本屋に行き、コーヒーを片手にLonely Planetラオスの政治・経済の項を読んだ。現在ラオスは経済開放政策を採っているが、それは理想的な社会主義を目指しての途中段階であり、将来世界が成熟した時に、社会主義が多くの国々に受け入れられるようになる、と政府は表明している。
しかしそんな時が来るのだろうか?
今後も数十年にわたってラオスは経済的に発展し、生活水準も上がって行くと考えられる。そしてその駆動力になっているのは、周りの先進国(資本主義国家)の資本投入である。既にものが溢れている先進国では、後進国に先進国の概念を売り、資本を投入して海外進出しないと自国の経済力を保つことができない。この仕組みが資本主義の限界でもあり、この欠点に気付いた時が、世界が成熟した時なのだろうか。しかし絶対に世界に貧しい国はなくならないだろうから、社会主義の時代というのは永遠に来ないのではないだろうか、。
しかし、この2つのイデオロギーの衝突のために、冷戦の時代を通して世界中で何十万もの人々が犠牲となったことが信じられない。
Lonely Planetの前半部にあるその国の概要の内容はすごい。政治、経済、歴史、文化、教育等多岐にわたる項目が、数年毎に改訂され最新情報まで含む形で書かれているのである。その国のことを手っ取り早く勉強するために、これ以上適した文献はないだろう。
コーヒーカップも空になり、先ほど降り始めた雨が弱まったのを見計らって、私はHive cafeを後にした。
この後、ワット・ポーの山麓にあるTraditional Arts and Ethnology Centreをたずねた。ラオス少数民族の衣装や生活道具などが展示、説明されている博物館であるが、驚いたことに、入り口ではその説明が全て日本語訳されている冊子を渡してくれた。
一番興味深かったのは、山岳民族の結婚様式についてだった。伝統的には同じ集落の中で年頃の男女が出会い、日々の農作業や神事などを通してお互いを知り合い、結婚に至った。近年はそれが大きく変化し、異なる民族間の結婚、外国人との結婚もあり、説明文には、実際にそのような結婚をした二人にインタビューした話が書かれている。都心部の人々の生活が10〜20年で大きく様変わりするように、山岳民族の生活も時代に応じて大きく変わりつつある。
確かにその通りだ、と私はおもった。
父親がフランスの兵士と思われる金色の髪の色をした、村の女の子。
ラオス語で初等教育を受けているモン族、カム族の村の子ども達。
ルアンナムター出身でツムラ勤務の日本人男性と結婚したジョイさん(ともちゃんの友達。5月15日参照)
私の短い旅の経験からだけでも、山岳民族の生活が変化していることがわかる。しかし、山岳民族という言葉に、伝統的かつ永続的な何かを期待してしまうのは、あまりにも高速な時間の流れの中で生活している都市生活者ゆえだからだろうか。
ようやく太陽が一日の役目を終えて沈んでゆく時刻になり、ナイトマーケットには多くのお店が並び始めた。私はその雑踏の中を抜け、市場通りにある寺院の境内に入った。時刻は5時で、後30分もすれば夜のお勤めである読経が始まる。私は一人先に本堂の中に入って帽子を脱いだ。しばらくすると係りのお坊さんが現れ銅鑼を鳴らした。すると経典の教科書を持って老若交えたお坊さんたちがお堂に集まり、仏陀像の前に正座をしてお経を読み始めた。まるで歌のような読経は、胸の底に水琴窟の響きを思い起こさせる。目の前の仏陀像はそんな我々を静かに見下ろし祈りを受け止めているように見える。
私は6時少し前にそっとお堂を出て、その寺院を後にしたが、読経の心地よさはずっと心の中に残った。グリーンディスカバリーに戻るとスタッフの人たちは
「もう準備はOK? 彼がバスターミナルまで送っていってくれるよ。」
と言ってまだ若い丸刈りの男の子を指差した。彼は素早くお店の外においてあったバイクにまたがり、私に後ろに乗るように示した。
走り始めたバイクは群青色の夜風を切ってメコン川沿いを走る。夜の営業を始めたレストランの白熱灯が熱帯の樹木をぼんやりと照らす。トゥクトゥクやトラックのライトが、まるで蛍の光のように自分の両側を飛び交っていく。街の中心部を離れ、10分程走るとバスターミナルに到着した。
「ありがとう。とっても助かりました。」
「どういたしまして。どうぞいい旅を続けてください。」
笑顔でそう言った彼は、まだ中学生ぐらいの年齢だった。丸刈りだったことからして、つい最近まで僧生活をしていたのかも知れない。私が彼の肩につかまったのは大丈夫だったのだろうか、そう心配したのもつかの間、彼はまたバイクにまたがって軽く会釈し、颯爽と走り去った。
19時30分発、明朝7時ビエンチャン到着予定の夜行バスに私は乗った。車中はシートもリクライニングもぼろぼろで、車内灯も所々しかついてなかったが、冷房は程よく効いている。定刻どおり出発し、20分もするとバスは街灯のない山間部を走るようになり、私はいつしか眠りに落ちた。
数時間後、何の変哲もない道路わきにバスが止まった。乗客が立ち上がり次々と外に下りてゆく。何かと思うとそこはトイレ休憩のための場所だった。乗客は男女ともに、近くの草むらに行って用を足し、伸びをしてまたバスに戻ってくる。
すごい! ラオス風24時間営業のサービスエリア!
私も虫の声を聞きながら草むらで用を足し、伸びをしながら遠くの山間に灯る集落の明かりを見つめた。マン君と一緒にたずねたような村々の明かりだろうか。山岳集落はラオス全土にいくつぐらいあるのだろう。
その後夢うつつになったり、熟睡したり、起きて窓の外を見ているうちに、想像以上に早くバスは進んでいった。首都に近づくにつれ、誇らしげに屹立するコンクリートやレンガ造りの家々が増えて行く。
5月22日
そして6時30分に無事ビエンチャン北バスターミナルに到着した。バスを降りて有無を言わさずに乗せられたトゥクトゥク(かわいらしい絵柄のついた乗り合い小型トラック)だったが、いつまでたっても発車する気配がない。地図を見ると中心部まで歩けない距離ではない。痺れを切らした私は、客引きのおじさんの声を振り払って一人静かに歩き始めた。
大手を切って歩き始めたものの、中心部までは意外に遠かった。空港が見えた時点でまだまだパークビューは先であることがわかったが、いまさらトゥクトゥクを呼び止めるのも癪なので私は気長に歩き続け、約1時間半かかって8時過ぎにパークビューに到着した。
ともちゃん、りなちゃん、そしてマリベルさんが出迎えてくれる。私はシャワーを浴びて汗を流し、3人で食卓についた。テーブルの上に並ぶのは、お手伝いのコップさんが作ってくれた日本食の朝ごはん。ベビーシッターも兼ねてほぼ毎日働いてくれる彼女の存在は、ともちゃんにとって偉大である。
「ともちゃん、日本に帰国した後お手伝いさん無しで大丈夫?」
「そうなの。もうそれがすごく心配なの〜。」
彼女はりなちゃんの口に離乳食を入れながら答えた。
今日マリベルさんは国境を越えて、タイのウドンターニ空港から午後の便でフィリピンに帰国する。私は夜8時にビエンチャン発の便なので、まだ一日市内観光をすることができる。ともちゃんは二人の出発時間を鑑みて、まず私を買い物ができる朝市に送り、マリベルさんを市内のバスターミナルに送り、その後11時30に国立博物館の前で私を拾ってお昼は松崎さんも一緒に3人で食べるという予定を立てた。
ラオスで時間を共有できたことを感謝してマリベルさんに別れを告げ、アルンさんの運転でともちゃんと一緒に朝市に向かった。彼女いわく、地元の人も通うというビエンチャンの台所である朝市は、野菜、果物、魚介類、肉類、衣料品、お菓子など、広大な面積の中に数え切れないお店が並んでいる。ともちゃんに5000円を両替してもらい50000キープを手にした私はすっかり気が大きくなり意気揚々と車を降りた。
米屋の前には色んな種類のもち米が並んでいる。1キロ6000キープ(60円)と日本より遥かに安い。華僑の人のお店には様々な中華食材がおいてあり、その中には日本と同じ干し椎茸があった。魚介類のお店には日本で見るものとはどこか異なる甲殻類や魚類が並ぶ。隣国の食材を扱うお店もあり、思わずベトナムの春巻ライスペーパーとスイートチリソースを購入。
生活感が脈々と感じられる地元の市場は文句なしに面白い。ゆっくりと時間をかけて歩き回るうちに私のかばんはずっしりと重くなった。
その後国立博物館まで歩き、お土産の入ったかばんをフロントに預け、私は一番最初の部屋にある先史時代の展示を見た。ラオス北東部のシェンクワーンにジャール平原(Plain of jars)と名付けられた謎に満ちた遺跡がある。石製の大きなつぼがいくつも原野の中に転がっており、紀元前500年ごろから埋葬の地であったことが推察されているが、この慣習を行っていた民族については何1つわかっていない。
11時30分。予定通りにアルンさんの車が迎えに来てくれ、私は炎天下の道路上から冷房の聞いた後部座席に乗り込んでほっとした。ともちゃんが言う。
「お昼、何が食べたい? 可能性としてはラオス料理が食べれる屋台かちょっとおしゃれなフレンチか、おいしい中華って感じなんだけど、、。」
「うわ、悩むなあ。じゃあ最後だし、フレンチでお願いします!」
5分ほど街中を走り到着したそのお店は、褐色の壁、高い天井、そしてクリーム色の椅子が落ち着いた空間を作り出しており、バーカウンターには何十種類ものアルコールとワイングラスが並べられていた。既にテーブルに座っていた松崎さんが私達に手を上げた。ここのお店はJICAに訪問者が来たときによく使うという。ランチコースが800円〜というラオスではちょっとした高級レストランである。
白ワイン、おしゃれな器に入った野菜の冷スープ、ハーブと鮭のグリルを堪能しつつ、私は撮った写真を見せながら山岳民族のツアーのことを話した。
「なつかしいなあ。僕が2年前にルアンナムター近郊の山岳トレッキングに行ったのを思い出すよ。えっ、こんなコンクリート作りの家なんてあったんだ。」
「そうなんです。ここの集落は車の通れる道路とつながっていて一番開発が進んでいる村でした。2年後には電気も通る予定だそうです。なんか、昔ながらのものが失われていくのは悲しい気がするんですけど、でも住んでる人にとったら便利になるのは大歓迎なんですよね。」
「そうなんだよ。山岳民族の暮らしも実は流動的で変化しつつあるんだよね。」
いつの間にかともちゃんの手を離れてとことこ歩き出したりなちゃんをお店のお姉さんがあやしてくれる。フレンチのレストランでもラオス気質は健在である。
お昼の後は再度国立博物館に送ってもらい、ラオスの仏教文化の展示を丹念に見た。
ヒンズー教と仏教の共通点、差異、分化して伝播していった経緯。謎と興味は深まるばかり。
2時にともちゃんが迎えに来てくれ、今度はラオスの民族衣装を着て写真の撮れるフォトスタジオへ行った。京都の舞妓さんフォトスタジオのラオス版である。
ともちゃんは友達を連れて何回も来ているのでカウンターのおじさんとは顔なじみで、その横を通って私たちは2階の衣裳部屋へ通された。右側にはラオ族の民族衣装が並び、化粧品が並んだ鏡台があり、前方には写真を撮るための背景となる舞台があり、長いす、傘、花瓶などの小道具が並ぶ。ここでこれから何が始まるのだろう!緊張してどこに立ったらいいか戸惑っていると、化粧を担当する女性が入ってきて、鏡台の前に向かうように指で示した。
「このおばさん、毎回すごく無口なんだよね。でも腕は確かだよ。」
と入り口近くに座ったともちゃんが言う。そのおばちゃんは好きな色の洋服を選べとともちゃんを介して私に言った。
「じゃあ赤で。」
彼女はそれを受け取り、巻きスカートの裾の高さを合わせながら私に着せた。次は化粧である。彼女は相変わらず一言も発せずに淡々と私にファンデーションを塗り、頬にわずかに紅色をのせ、眉を書き、アイシャドーを用いた。指で「鏡を見なさい。」といわれ近づけて見ると、おお!これはかなりの変身ぶりである。そして彼女は私の髪に付け毛を加えて纏め上げ、その上に洋服と同じ赤い色の冠をつけた。
今度はカメラマンのおじさんが来て、背景の幕の前に立つようにいう。さらにギターを持つよう言われ、その指先と首の角度を直されて、一枚撮影。
おじさんが壁際のボタンを押すと、背景幕が自動的に上がり、その後ろから新たな背景幕が現れる。その度に私は別の小道具を持ち、計0枚ほど写真を撮ってもらった。
三十路を過ぎての初めての変身フォト体験、想像以上に面白い。階のカウンターでは撮った写真の中から好きなものを5枚選んでプリントアウトしてくれて、値段は全部で500円。
この後、フォトスタジオの向かいにある市場を歩き、閉店間際の洋品店でラオス風の刺繍が施してある黒いスカートを買った。民族衣装によく見られる幾何学模様が4種の色で黒い生地の上に表現され、ちょっとエスニックなスカートとして会社に通勤するときにも着られそうである。帰国したら、無事に再就職先が決まっていますように、、私はそう願った。
この後パークビューに戻り、仕事から帰ってきた松崎さんも一緒にお手伝いさんの作ってくれた夕飯を食べた。りなちゃんがうれしそうに部屋の中を駆け巡る中、松崎さんが言う。ラオスは、経済発展による貧富の差の拡大とともに犯罪も増えている。しかし未だにビエンチャンはJICAの駐在先としては最も安全な町の1つである。
「夏からはしばらく日本勤務になりますけど、また機会があればアフリカでもどこでも駐在して働きたいですね。」
それが実現することを心から願う。小さい頃から外国の雰囲気を吸収して育つりなちゃんは、どんな風に成長していくのだろうか。
私の飛行機の時刻に合わせて、1850分頃に車で出発し1900に空港到着。首都圏が小さいが故に、空港へのアクセスも非常に良い。チェックインもスムーズに終わり3人で最後のビアラオを飲む。ともちゃんは改めて、マリベルさんとの旅行が難しかった、、とため息をつく。そんな中、りなちゃんを片手に抱きつつ、私の面倒も見てくれた彼女に心から感謝である。
「日本に帰ってきたら、連絡頂戴ね。今回は本当にありがとう。」
ともちゃんと松崎さんは、出国審査の手前のところまで送ってくれ、私は何度も振り返って手を振った。